トップ > 国際室 > 各種イベント報告 > 2006年夏季英語集中講義
2006年夏季英語集中講義
![]()
The 5th International Engineering Communication
― 夏期英語集中講義を総括して ―
国際室 廣瀬 幸夫
はじめに
2006年9月、昨夏に引きつづき、夏期英語集中講義「The 5th International Engineering Communication」を実施した。 オーストラリア/シドニー工科大学から3名(Helen McGregor 先生、David Eager 先生、Paul Maloney 先生)の講師を招き、 同校で実施している講義を大学院理工学研究科国際開発工学専攻の開講科目として一週間集中開講するプログラムである。 受講生は日本にいながら海外の大学と同じ講義を受けることができることで、年々本講義の認知度が高まっている。 5回を経過したこの時点で、本講義を総括することにより、次の展開に繋げたいと考える。
これまでの経緯
初回の開催に先立ち、2002年12月、協定校であるシドニー工科大学を訪問し、 学生の英語コミュニケーション能力の向上を意図した英語講義が開講可能か、予備検討を行った。 幸い、シドニー工科大学の窓口教員である Maloney 先生の賛同を得、具体的な企画を行った。 シラバスの検討に始まり、海外大学との一括業務委託契約や外貨支払い方法などについて、 現行の客員教授招聘制度を用いない新たな方法が導入された。
表1は過去5回のプログラムを比較したものである。第1回は2科目を各1週間ずつ2週間連続で開講した(詳細は、クロニクル2003年11月号 P11参照)。 学生の負担が過大であり、より多くの学生が受講できるように配慮し、2回目からは2科目を平行して開講した。 開催場所をすずかけ台に移したが、春休み期間の行事(論文発表会など)と重なったため受講者を集めることに苦労した。 以後、春休み期間の開講を避け、年1回の夏期集中講義とした。
表1 英語集中講義の各回毎の比較
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 平成15.9.8~19 (12日間) |
平成16.2.16~21 (6日間) |
平成16.9.20~25 (6日間) |
平成17.9.12~17 (6日間) |
平成18.9.11~16 (6日間) |
| 立上専攻 | 化学工学 (鈴木正昭先生) |
生体システム (広瀬茂久先生) |
国際開発工学 (廣瀬幸夫) |
国際開発工学 (廣瀬幸夫) |
国際開発工学 (廣瀬幸夫) |
| 会場 | 大岡山 (西8号館) |
すずかけ台 (B 棟) |
大岡山 (石川台1号館) |
大岡山 (西9号館) |
大岡山 (西9号館) |
| 受講者数 | 10名 | A 15名 B 15名 |
C 15名 D 10名 |
A 18名 B 16名 |
A 18名 B 18名 |
| 応募者数 | 40名位 | 35名位 | 31名 | 56名 | 65名 |
3回目は、参加しやすい時期を予想して、できるだけ秋学期が始まる時期に近づけて開講した。大学院時間割表に掲載され、学生への周知度が高まった。しかしながら、祭日と2日間重なり、建物の入口の鍵が施錠されるなどの学内施設を利用する上で不都合が多かった。4回目は、時期を1週間繰り上げたが影響はなく、多くの学生が応募した。このため、選考基準をより明確にし、TOEIC または TOEFL スコアを所持している学生を優先した。今回(第5回)は、第4回とほぼ同様な時期と講義内容であった。ただし、夏休みの予定が立たないので受講決定時期を早くして欲しいとの学生の要望に応えて7月末に決定をして応募者へ通知した。
受講者の選抜方法
本講義の開催案内を国際室長、専攻長連名で各専攻長宛にメール伝達すると共に、学内掲示板を利用して周知した。 応募締切日近くに応募が殺到するため、参加希望を強くもつ学生には先着優先などの道を拓くなどの対策が検討余地としてあろう。
講者は英語検定スコア上中級者から選抜し、講義レベルを確保した。 こうした集中講義の受講機会増加が、本学が進める TOEIC/TOEFL スコア取得のインセンティブとなる。 申込用紙に記載してある応募者の TOEIC/TOEFL スコアから TOEIC 換算700~800点が全体の半数以上を占め(図1)、 年々応募者の英語レベルが高くなっている。選考基準は、第1回から大きく変わっていない。 1.大学院博士課程及び修士課程の院生を優先とする、 2.英語講義の受講能力があること(TOEIC スコアーが650以上であり、志望動機の Essay の判定が B 以上)、 3.全講義日参加が可能であること。 応募者と受講者の所属毎の結果を専攻別に表2にまとめる。 25の専攻から65名応募があった。その内訳は、院生56名のほか、学部生が7名、研究生が2名であった。 各研究科からの応募数にバラツキはあるが、 全研究科から応募があったことから周知方法(専攻長へのメール、学内掲示など)に問題はないと考えられる。
図1 応募者のTOEICスコア一覧
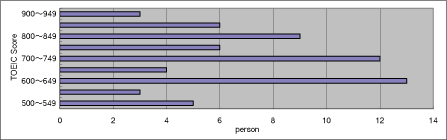
表2 応募者と受講者の所属 (分数 : 受講者数/応募者数)
| 理工学 | 社会理工学 | 情報理工学 | 総合理工学 | 生命理工学 | イノベーション | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械物理 | 1/2 | 経営 | 2/2 | 情報 環境学 |
2/2 | 物理情報 システム |
1/1 | 生体 分子機 |
1/3 | 技術経営 | 4/7 |
| 国際開発 | 3/6 | 価値 システム |
1/3 | 計算工学 | 2/3 | 人間環境 システム |
1/2 | ||||
| 機械制御 システム |
3/3 | 環境理工 | 2/2 | ||||||||
| 応用化学 | 1/1 | 物理電子 システム |
1/2 | ||||||||
| 建築学 | 1/1 | 創造 エネルギー |
1/1 | ||||||||
| 土木 | 0/1 | メカノマイクロ | 0/1 | ||||||||
| 集積 システム |
1/1 | 知能 システム |
1/1 | ||||||||
| 電気電子 | 1/1 | ||||||||||
| 有機 高分子 |
1/2 | ||||||||||
| 材料 | 1/4 | ||||||||||
| 原子核 | 3/3 | ||||||||||
| 機械宇宙 システム |
1/1 | ||||||||||
| 計 | 17/26 | 3/5 | 4/5 | 7/10 | 1/3 | 4/7 | |||||
受講者は博士課程が5名、修士課程が31名、計36名であった。 受講者の国籍は、日本(27人)、中国(4人)、韓国(1人)、ベトナム(1人)、イラン(1人)、インドネシア(1人)、 バングラデッシュ(1人)であった。講義名に相応しい「international」な雰囲気であると受講者がアンケートに寄せている。 受講者の男女別は男性が27名、女性が9名。クラス別では女性が 1/3 を占め、比較的女性への人気度が高い結果となった。
本講義の内容
プログラムのテーマは工学分野におけるコミュニケーションとマネージメントである。 国際的技術者としての話し方、思考と理論付け、文書化、プロジェクト管理、発表の仕方などを中心に授業展開している。 実施期間は、平成18年9月11日(月)~平成18年9月16日(土)、 実施場所は、大岡山キャンパス西9号館3階 講義室 W932及び W933である。 授業科目は以下の2科目で、用いた教材はシドニー工科大学の講義と同様、以下の本を用いた。
- Communicating as Professionals (Edit., Thomson Publishment)
- Project Management (Edit., McGraw Hill)
講義は、毎日異なるトピックをもとに小グループ毎に発表する。 1日1回は前に出て皆の前で5‐15分位発表をするため、1週間が終わる頃には、英語で発表することの自信をつけた学生が多かった。 同時に、発表に対して、先生から的確な指摘があった。 例えば、質問をすることが聞いた人のエチケットである、質問の内容を質問者に応えるのではなく、 聞いている人全員に質問の意味を確認して全員に向かって応える、など我々教師が受講してもためになる内容であった。


まとめ(成果と今後の取進めに代えて)
本講義は本学における海外大学との教育連携の先鞭を付け、学生の英語コミュニケーション能力養成促進に着実に役立っている。 従来、中上級者向けの英語集中講座がなく、受講した学生の評価は高い。 本学の正規講義で味わえない刺激と英語によるグループ活動に対し、学生は高い評価を与えている。 外国語研究教育センター(外セ)が実施している科目「国際コミュニケーション科目」との整合性(カリキュラムの位置付け) をつけることが費用対効果を高めるために緊要であり、外セとの話し合いを開始した。今後両者の科目を比較し得失を明らかにし、 国際教育の観点から本講義の独自性をさらに明確にする。 受講した学生が TOEIC に再受験したり、派遣留学などに応募するように、 本講義を通して系統的なキャリアアップを明示していくことも必要であろう。
講義の評価結果・学生の声 ![]() (19KB)
(19KB)
