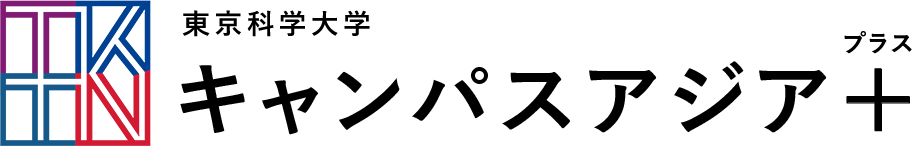午前10時7分。
気温は29度。
これを書いている時点で天気予報では一日快晴となっているが、空には既に灰色の雲が立ち込めている。天気予報は基本当てにならない。
朝は静かなようでいてそんなことは全くなく、概ね午前9時ごろまでマイナバードと呼ばれる鳥が終末期のセミのような鳴き声を発し続け、10時以降は別の何らかの生物の鳴き声、そしてトラックの音で私の部屋は満たされる。
日の出は概ね午前7時に始まり、刺すような日光と70%を超える湿度の1日が始まる。
シンガポールの日光は赤道直下故にかなり強く、紫外線量も日本の2-3倍だそうで、この線量は世界2位らしい*1。UVインデックス指標を見てみると8という数値。これは指標としては上から2番目の「非常に強い」に該当し、気象庁のサイトによると「日中の外出をできるだけ控えよう」になる
*2。北半球の紫外線量に慣れきった我々日本人がなんら肌対策を施さなかった場合、自ずと死を迎えることは間違い無いだろう。
シンガポールの人は基本的に親切な人が多く、人当たりのいい方が多い印象がある。そしてコミュニティとしての結束が強く、大学のサークル一つとってもかなり高度な組織運営(スポンサーを募ったり会社のようなビジョンやミッションがあったりなど)がなされているような印象がある。ではこのシンガポールの人々の親切心を築いた道徳観念、そして一見難しそうに見える多民族の巧みな組織運営能力はどのようにして育まれてきたのだろうか。シンガポール政府が公にしているシンガポールの歴史に関する記述によると*3、このようなシンガポール国民の特性を築く上では様々な教育的努力がなされてきたようである。まずシンガポールでは1970年代において、国民のモラルの低下や文化喪失(deculturisation)に警鐘を鳴らし、1984年に宗教教育が中等教育段階で必修とされた*4。これによって宗教の道徳的価値観を吸収し、国民のモラル形成を図ったが、同科目の導入後の宗教熱の高まりに伴う宗教間での確執が顕在化したため、同科目は廃止される。科目の廃止以降は多民族国家において宗教教育は画一的に行うべきではなく個々の家庭で行うべきだという方針に転換がなされ、1990年以降Civics and moral educationという必修道徳科目が導入された*3。Civics and moral educationは生徒に個人よりも全体への意識を持たせることで他者との調和を重んじる姿勢を養育し、多民族国家シンガポールに貢献する人材を育てることを目的としている。これらを達成するために、Civics and moral educationでは民族間、宗教間のつながりを強固にしシンガポール市民としての責任感を持たせるとともに、国家への忠誠心を育む教育を行なっているようである*3。この教育が功を奏したのか、他の要因も存在するのか不明だが、概してこの教育政策によってシンガポールは、複数の宗教背景を持つ道徳観念を形成しつつ、その道徳観念がシンガポール国家の安定に貢献するようなシステムを形成することに成功しているように見える。そして恐らくこれがシンガポール国民個々の多民族(他者)
への親切心と多民族を束ねる能力の高さにも影響を与えているのではないかとも思う。今回は政府の教育政策に焦点を当ててシンガポール国民の道徳観念を調べたが、他にも気候であったり、兵役のシステムであったり諸々が絡んでいそうなので、そこはゆっくり4ヶ月間で知ることができたら良いなと考えている。
*1.Odys global,sunburn map
*2.気象庁,UVインデックスとは
*3.Singapore government, HISTORY SG,"Civics and moral education Introduced"
*4.金井里弥,"シンガポール中等学校における道徳教育の特質一「公民・道徳
教育」の実態に着目して一",(2010),日本教育学会第69回大会
 (寮に住んでいる猫。寮生が積極的に世話をしている)
(寮に住んでいる猫。寮生が積極的に世話をしている)