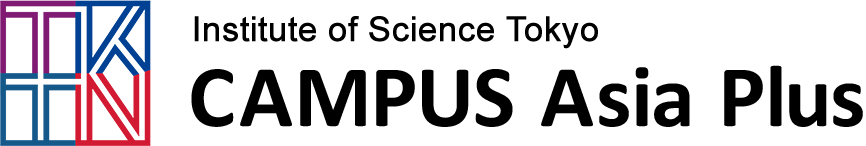私はよくオンラインプラットフォームでビジネススクールのjob marketに関する紹介を目にしますが、job marketの全過程を完全に体験した記述は少ないです。ビジネススクールの学術就職市場は高度に制度化された特徴を持っています。他の学問分野と比較して、ビジネススクールの採用プロセスはより規範化・統一化されており、通常 Online面接—キャンパス訪問(flyout)—オファー提示という標準的な流れに従います。
日本においては、私の観察する限り、経営学系やビジネススクールの大半は公開的な国際job marketを持っていません。今年、一橋大学で類似の募集があったのを見かけましたが、これは日本の大学も積極的に国際化を進めていることを示しています。しかし、ある意味では日本の大学はビジネススクールの国際採用において依然として存在感が薄いと言えます。重要な理由の一つは給与水準の低さです。ビジネススクールの助教は通常グローバルペイで、およそ2,000万円程度が相場です。この水準の給与を実現するには、ビジネススクールは十分な寄付金、高額なMBAやその他の修士課程による収入、そして政府からの助成金を維持する必要があります。通常、日本の国立大学の学費は固定されているため、学生の学費から十分な資金を得ることはほぼ不可能であり、この点が高収入・高支出モデルを支えられない一因となっています。そのため、トップビジネススクールの卒業生を日本での応募に引きつけることは難しく、海外にいる日本人ビジネス博士でさえ海外での就職を優先する傾向があります。
日本のビジネススクールについての話題は議論する価値が大いにありますが、それはこの日記の主題ではありません。job marketにおいて最も重要なプロセスはflyoutです。キャンパス訪問の期間は2〜3日間です。採用側の大学は通常、初期面接の候補者の中から5〜7名を選んでflyoutに招待します。この数はさらに少ないこともあります。flyoutの旅費は採用側の大学が全額負担する必要があるため、初期選考段階での競争は非常に激しく、flyoutの招待を受けること自体が候補者が最終候補リストに入ったことを意味します。
flyoutをマラソンに例える人もいますが、これは決して大げさではありません。いわゆるキャンパス訪問とは、単純な意味での大学見学ではなく、学生、学科長、他の教員との対話、食事、プレゼンテーションが求められます。例えば、典型的な2日間のスケジュールは以下の通りです:
1日目:
• 午前:学科長との面談、学部・学科の紹介
• 午前〜正午:4〜5回連続の教員との個別面談
• 昼食:一部の教員とのワーキングランチ
• 午後:博士課程学生とのグループトーク
• 夕方:Job Talk
• 夜間:懇親ディナー
2日目:
• 午前:学部長または副学部長との面談
• 午前〜正午:残りの教員との面談
• 昼食:若手教員または助教との交流
• 午後:模擬授業(一部の大学で要求される)
• 夕方:キャンパスまたは市街地の見学
このスケジュールのあらゆる要素が極めて重要です。多くの人は学科長や学部長との会話が最も重要だと考えるかもしれませんが、実は博士課程学生からのフィードバックも非常に重要です。大学は博士課程学生に候補者を評価させ、点数をつけさせます。候補者が話しすぎて博士課程学生に対して冷淡な態度を取ったり、十分な敬意を払わなかったりして、最終的にオファーが取り消されたケースもあると聞いたことがあります。大学が手配する昼食や夕食での会話は、採用国の風土や習慣、結婚・育児の経験、個人的な趣味などの話題に及ぶことが一般的です。実は、食事の会話は学術的な会話よりも恐ろしいと私は感じています(笑)。さらに隠れた評価項目として、SNSがあります。これは現地の博士課程学生から聞いた話ですが、候補者が公開しているSNSも評価要素として見られることがあるそうです。
Job Talkはflyoutの中で最も重要なプロセスであり、通常75 -90分間続きます。候補者は学部全体の教員・学生に対し、自身の最も成熟した、最も影響力のある研究成果を発表する必要があります。これは研究の質を試すだけでなく、候補者の学術的表現力、臨機応変な対応力、問題処理能力の総合的な検証でもあります。Job Talkでの質問はしばしば非常に鋭く、挑戦的なものです。これは学術文化の表れであると同時に、候補者のストレス耐性を試すものでもあります。時には、候補者の業績が非常に優れていても、job talkで問題のある研究をテーマに選んでしまった場合、失敗に終わることもあります。このプロセスを経て、最も優秀な人材のみが最終的なオファーを獲得できるのです。
総じて、Flyout文化は厳しいものですが、ビジネススクールの研究者の粘り強さとストレス耐性を育んでおり、トップビジネススクールが世界中から最も優秀な人材を採用することを可能にしています。さらに、一部のアジアの大学に存在する内定による採用と比較すると、このプロセスは比較的透明で標準化されています。候補者は評価基準とプロセスを明確に理解しており、採用委員会もflyoutでのパフォーマンスに基づいて集団的意思決定を行う必要があります。この透明性は、ある程度採用の公平性を保証しています。私たちは皆、科学大が総合大学への転換に向けて努力していることを知っていますが、将来的に科学大が同様のjob market制度を導入し、国際採用に参加して、より多くの人材を惹きつけることを期待しています。
PIC: NBS Main Building