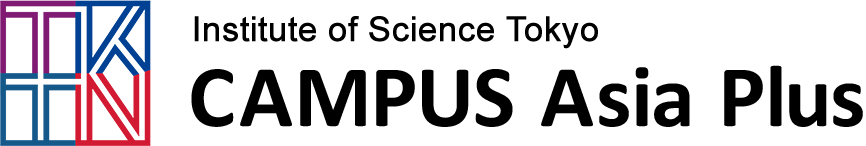日本は最近急激に寒くなったようですが、シンガポールはさすが常夏の国ということで、最高気温は30度に張り付いています。身体が日本の気候に合わせようとしているのか、最近は夏ごろよりも暑く感じます。私も残り1カ月ほどで帰国となりますが、この暑い状態から解放されるのはうれしい一方で、いきなり冬になるのは少し想像できません。
そんなことを考えるくらいには帰国のことを考えることになった時期ということで、今回は留学の振り返りをしてみます。
◆講義について
私は、今研究室で研究している内容の基礎だけれども、これまで講義でしっかり学んだことがない分野について講義を受けていました。
講義の内容については、研究を行うにあたってゼミや自習である程度知識をつけている分野だけれども、講義として系統立てて学んだことがないというだけだったため、ある程度戦えるものかなと思っていたのですが、おおよそ予想通り何とかなったという印象です。ただ、他の日本人留学生の話を聴いていると、関係がある分野であっても(特に文系の人は)何を言っているのかわからないと言っていた人もいました。
これについては専門用語が前もって英語でわかっていたかがかなり効いているのかと思っています。私は、研究にあたって英語論文を読んでいたし、そもそも日本語でも用語としてカタカナ、アルファベットがよく使われる分野で、日本語の用語も英語の直訳のような場合が多いように思います。おそらくこの記事を読んでいる多くの方は同じような境遇ではないかと思うので、分野外の講義を選ばなければ、ついていけるのではないのかなと思います。
ただ、講義の構成については日本と大きく異なると思います。科学大の講義だと、毎週宿題が出て、中間試験と期末試験があるというだけの場合が多いと思います。NTUでは、中間試験と期末試験はある一方で、グループワーク×レポートorプレゼンテーションのようなグループワークがある講義が多いです。レポートと中間、期末をベースに割と点数が決まっているようで、かつこれらは7週目、13週目、テスト週間に集中的にやってくるので、この近辺はみんな忙しそうにしていました。
◆英語について
ご存じの通り、シンガポールの英語はシングリッシュと呼ばれ、特徴的です。おそらく中国語訛りだと思うのですが、時には本当に聞きづらく、日本人的には全く理解できない場面も多くあります。私もグループワークでディスカッションをしたときに、本当に何を言っているのかわからず、何度も聞き返したりしていました。
しかし、砕けた場面で砕けるだけで、きちっとした場面では割と聞き取れるように感じる場面が多かったです。教授陣もシンガポールの訛りがあるはずですが、授業の時には全くそれを感じませんでした。地方出身の私にしてみれば、方言と標準語の使い分けに似ているかもしれません。政府はシングリッシュを嫌っていると聞きますし、おそらく方言と同様に皆訛っているという自覚は持っていて、特にエンタメなどで流れる英米の一般的な発音はわかるし、できる(ただ抜けきらない)みたいな状態なのではないかなと推察しています。
この4か月間で、シングリッシュを完全に聞けるレベルには至らなかったですが、むしろ自分のジャパングリッシュともいうべき英語を堂々と話してもいいのではないかと思うようになりました。私が聞き返すようにあちらも聞き返すし、意味が通っていれば理解はしてくれるという点で、どんどんと話してコミュニケーションをとっていこうというマインドに変化していきました。グローバルスタンダードと呼ばれるものに合うまで何もしないよりも、自分流でやるだけやっていくという心構えがグローバルスタンダードに向かっていく方法なのだと気づかされました。
◆学生交流について
留学の中で友達ができるか不安に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、これに関しては、日本と同じくらいの難易度だと思います。接点としては、日本と同様に授業や、クラブ、そのほかの課外活動のほか、寮でのつながりなど日本にはない接点もあると思います。言葉の壁はあるけれども、カタコトの英語であっても話を聴いてくれるくらいにはシンガポールの人は優しいので、問題ないと思います。
留学生同士の交流は思っていた以上にあったと感じます。NTUとNUS、SMUの3大学に留学している日本人留学生の会があり、たまにこの会でイベントが開かれたりしていました。海外で生活する中で、日本語で相談できる人たちがいるというのは心強いなと思います。
◆生活について
シンガポールの生活は、基本的には便利で、困ることはありません。これまでのブログで散々述べてきたように、インフラはしっかりしており、食事は多国籍で美味しく、日本シックになるようなことはないです。しかし、日本人とは根本的に文化が異なるのだと思う場面がいくつもありました。
最も違いを感じたのは、衛生観念の違いです。大学内を含め、ホーカーセンターと呼ばれる屋台街を発祥とする食堂が多くありますが、いずれも屋根がついているだけの屋外である場合が多いです。日本の飲食店は、テラス席はあっても、基本周囲を壁に囲まれた場所で食事をすることになると思いますが、ホーカーセンターは、屋外なので鳥やハエなどが平気で自分の周りを飛び回ります。机も吹いてくれる清掃員がいるけれども、毎回完璧に綺麗というわけではないです。調理場もすごく綺麗というわけではなく、一部の店舗は現地の衛生管理はクリアしていても、日本の衛生基準だときっと厳しいと思われる場所もあります。こういったものに慣れるところまではいかなかったですが、リスクコントロールをするために、清潔そうな場所を選ぶなど自分でちゃんと管理しようとする心構えはついたと思います。
今回の留学を通して感じたのは、「環境の違いを受け入れながら、自分なりのやり方で適応していくこと」の大切さです。講義や生活の中では、日本とは異なるスタイルや文化に戸惑うことも多くありましたが、その一つひとつが、自分の柔軟性や主体性を試す良い機会になりました。英語についても、完璧さを求めるよりも、自分の言葉で伝えることの方が大切だと気づき、積極的に発言する姿勢を身につけることができました。
また、異なる背景を持つ人々と学び、協力する中で、多様な価値観に触れ、それを尊重しながら自分の意見を持つことの重要さを実感しました。シンガポールという多民族国家での経験は、国際社会の中で生きていく上での基礎となる視野を与えてくれたと思います。
この留学で得た学びと経験を糧に、今後も新しい環境に臆せず飛び込み、自分の可能性を広げていきたいと思います。