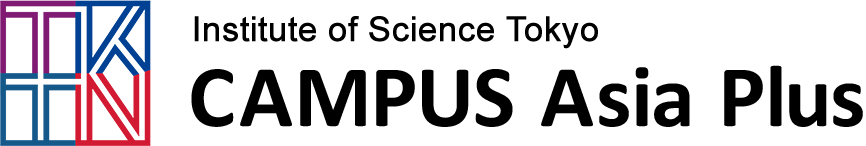9月が終わり、シンガポール生活も二か月が経ちました。
今のところ、お気に入りの料理は麻辣香鍋(マーラーシャンゴ)です。日本でも流行っている麻辣湯の汁なしバージョンのような料理で、オススメポイントが二つあります!
一つ目は、自分で具材を選んでトッピングできるため、野菜をたくさん食べられる点です。これは麻辣湯のシステムとよく似ていますね!
二つ目は、麻辣湯とはまた違う魅力で、大皿で提供され、複数人でシェアできる点です。みんなで具材を選ぶのも楽しいですし、汁なしなので麺が伸びることもなく、話しながらゆっくりご飯を楽しめます。
日本でも冬は鍋のようにみんなで一つの料理を囲む文化がありますが、夏にはあまりそうした文化がないように感じます。
麻辣香鍋は、そんな季節にぴったりの新しいビジネスチャンスになるかもしれません(笑)
こんにちは、久しぶりです。
私はキャンパスアジア+プログラムで、2025年8月から12月までNTU(南洋理工大学)に留学しています。今回はシンガポール留学の教育環境の魅力をお届けします。
1. 文化的にオープンな環境
何と言っても、シンガポールの魅力の一つは多文化共生社会であることだと思います。
大学に限らず、日常生活でもさまざまなバックグラウンドを持つ人々と接する機会が多く、その多様性は私にとって大きな刺激です。
異なる文化や価値観を持つからこそ、問題意識や視点も多様で、話すたびに新しい気づきがあります。私の研究室には12の国籍の学生が在籍しており、各国のお菓子をいただくのも楽しみの一つです。
日本ではあまり意識しない細かな言葉の定義や、解釈の差を体験できるのは、将来、異なるバックグラウンドの人々と働く上で貴重な経験になるだろうと感じています。
2. ディスカッション中心の授業スタイル
私が現在受講している大学院の授業は、基本的には知識伝達型ですが、最終評価はプレゼンテーションで決まります。
このプレゼンテーションでは、3〜4人のチームで1本の論文を読み込み、内容を分析して発表します。評価項目が細かく決まっており、それに沿って現在プレゼンを作成しています!
他の学生から聞いた話で面白いと思ったのは、「Interdisciplinary Collaborative Core(ICC)」という授業です。異なる分野の学生がチームを組み、課題解決に取り組むそうです。東工大の立志プロジェクトに少し似ているかもしれません。
こうした授業からは、知識を学ぶだけでなく活かす教育の姿勢がうかがえます。ディスカッション型の授業を経験すると、他者の意見と比較しながら自分の意見の根拠を説明する必要があり、その過程で自分の価値観や興味を整理する助けになりますよね。
学士課程で留学していたら受講してみたかったです…
3. 学習モチベーションの高さ
シンガポールの学生は学習モチベーションが高いと言われています。
私自身の観察では、これはシンガポールの教育システムが学生の学習意欲に大きく影響しているためだと感じています。シンガポールでは、小学校・中学校・高校の各段階で進路に大きく影響する試験があり、勉強しないと将来に影響するという外的なプレッシャーが、学習意欲の一因になっているのかもしれません。
一方で、自国の発展に貢献したい、世界でトップになりたい、といった内発的なモチベーションを語ってくれる学生もおり、いつも刺激を受けます。
小中学生の場合、試験があり学力順に選択肢が豊富に用意されている分、モチベーションは日本より高くなる傾向があると感じました。しかし、大学生になると日本と同様、人によって差があるのかもしれません。
4. NUSとNTUの違い
シンガポール留学では、NUSとNTUのどちらを選ぶか迷う人も多いと思います。
NUSについてはルームメイトの話から知ることが多いです。彼女によると、NUSは全体として競争的な雰囲気を感じたそうです。ルームメイト自身は「ストイックすぎる環境が自分には合わなかった」と感じ、最終的にNTUを選んだとのことです。
一方で、研究室の学生の話では、NUS全体が特別に競争的というわけではなく、専攻や研究室によって雰囲気は異なるそうです。NTUでも人気の学部では競争がある場合があるため、どちらが良いかは一概には言えません。どちらの大学も、質の高い教育環境を提供しています。
個人的な意見ですが、NTUはシンガポールの観光の中心地から離れているため、勉強や研究に集中できる環境です。友達は「ジャングルの中に大学がある」とよく言っており、その名の通り、カワウソやリス、サルなど様々な動物に出会うことができます。動物・自然が好きな方には、NTUがおすすめです!
本日はシンガポール留学の教育面の魅力や日本との違いをお届けしました。
これからも様々な文化に触れてそれぞれの良さを考えていきたいです。