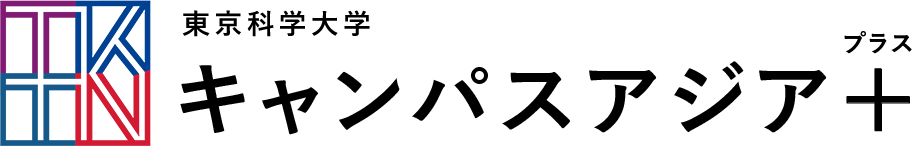活動紹介
留学体験談 清華大学
もっといたくなる、清華大学

山田 竜也
① 留学先大学(機関)の概略
アジア大学ランキングで安定して1位を取る大学です。構内はとても広いため、自転車かスクールバスで移動します。食堂の数も多く、様々な料理を食べることができます。北京の観光地の一つでもあり、休日になると多くの観光客がやってきます。
② 留学前の準備
私の場合は半年だけなので東工大での研究は出発前にデータを取り、留学先では論文執筆ができるようにしました。就活では、インターンは学部時代から行っていたため、帰国後に説明会や面接に挑むこととしました。
ビザについてはできるだけ早く応募しました。ビザ申請書には渡航期間が必要ですが、あくまで目安なのでビザ期間内に渡航期間が収まれば大丈夫です。
身体検査についてですが、半年だとレントゲン写真は不要でした。東大病院で受けると代々木より少し安いです。
役に立ったかは分からないですが、一応少しの日常会話は練習しました。事前に有道という翻訳アプリで日中翻訳をダウンロードしておくとオフラインでも使えます。
研究をしたい方はアポを取る必要があるのですが、私は7通ほど送り希望した研究室のアポは1件のみでした。多くは返事がなかったのですが、もしかすると英文メールを送ったことも理由かもしれません。清華大学の先生は英語を話すのが苦手な人は多かったです。もし返事が来なくて不安であれば中国人に助けてもらいながら中文でメールを送るのも手かもしれないです。
大体は現金が使えるので、事前に新宿西口の安い金券ショップで両替しておきましょう。
③ 留学中の勉学・研究
私は大学院生なので研究室に所属して研究を行いました。中国語の授業を受講しようと思いましたが、定員がいっぱいになり受講できませんでした。授業を履修したい方は気をつけてください。授業登録はしなかったですが、都市計画の授業を聴講しました。自然法則に即して都市のあり方を考える自然城市という概念を学びました。
研究では自分の専門であるパワーエレクトロニクスを鉄道の電力供給に応用した研究を行いました。研究室ではエンジニアの方が基板などのハードウェア設計やコードの作成を担当しており、人が多い中国の良さを活かして研究の効率化がされていると感じました。中国は研究スピードが早いため、学生や先生はとても忙しそうにしています。土曜日にもミーティングがありました。
④ 留学中に行った勉学・研究以外の活動
旅行にはたくさん行きました。まずはルームメイトと天津に行って慣れました。その後、中秋節に1人で1週間満州に行き、一人旅にハマってしまいました。中国人は話すのが好きなので、1人で夜行列車に乗るとよく話しかけられます。日本人で清華大学に通っている、というととても興味を持ってくれて会話が弾みます(もちろん翻訳アプリを通してですが)。最後は写真撮ったり微信交換して友達になることも多いです。中秋節の旅行で知り合った子とはその後に一緒に旅行したりして、今でもたまに話します。
鉄道が好きなので、研究の予定が2,3日空きが出ると鉄道で出かけ、半分くらいの省/特別市には行きました。丽江発の夜行列車の酒吧车で民族ダンスを踊ったり、列車で船に乗り海南に行ったり、北朝鮮を見に丹东に行ったりしました。
他にも研究グループ主催のスキーや、日本人会の飲み会なども楽しかったです。
日本にいるとメディアの報道などにより中国は危険な国と思ってしまいますが、実際にはスマホや財布を置き去りにしてしまうほど治安はいいです。
⑤ 留学を終えて、自分自身の成長を実感したエピソード
中国語が話せない状態で出かけて何かあったら捕まるかも、と最初は少し不安でしたが、鉄道に乗りたいという欲で外に出て回るうちに不安もなくなりました。2か月後には帰りの予定も決めずに弾丸で旅に出るようになりました。
研究においては、最初は先輩からの指示や教えがないと何もできませんでしたが、最後には自分で課題を見つけて検証するようになりました。
中国語も飲食店で注文できるくらいは話せるようになって、帰国後に研究室の中国人と話したら喜んでくれました。
⑥ 留学費用
渡航費、寮費、保険料は無料、奨学金は月6万円もらえました。最低限かかる費用としては、空港までの交通費、ビザ申請費、健康診断、食費、通信費(約75元)、洗濯(3元)です。私の場合は月7万円強使いました。
学食はとても安く、1食10元ほどで済みます。
鉄道も安く、北京地铁の初乗は3元、北京-郑州の寝台列車は163元です。
⑦ 留学先での住居
校内に寮はありますが、満室になったら申し込めないそうなので受付開始直後に予約しましょう。メールで案内が来ます。私の23号館は2人部屋でした。空調はあります。おばちゃんが掃除してくれます。水はそのまま飲むと危ないそう(最初の1日は飲んでましたが大丈夫でした)なので、備え付けのポットで沸かします。シャワーもあります。
出力の大きい電化製品は持ち込めないので注意しましょう。パソコンくらいなら大丈夫です。
1階にスタッフが在中していて、体温計や充電コード、絆創膏なども借りれます。
⑧ 留学先での語学状況
ほとんどが中国語しか通じないです。寮にいるスタッフの何人かと、清華大生の半分くらいは英語が話せます。あとは他の国の留学生とは英語で話します。留学生向けのイベントでは英語がメインです。
研究については、担当してくれた先輩が英語を勉強してくれたので、英語で会話できました。先生は最初英語で話して、途中から中国語になることが多かったです。中国語は聞き取れないことが多く、翻訳アプリを使いました。
⑨ 就職活動
オンラインで日本のインターンシップや説明会に参加しました。帰国後にも説明会に参加し、試験や面接に挑む予定です。私は行ってないですが、日本人会主催で企業の見学会もあります。
⑩ 留学先で困ったこと(もしあれば)
寮が二人部屋なので、風邪ひいて昼も寝たいときに電気が消せなかったです。
事前に連絡していた先生と実際に担当した先生が違ったため、春休みの開始時期が想定と違い、途中で帰らなければならなかったです。
北京は中国で交通事故の件数か死者数が一番多いです。自動車の運転マナーが最悪で、横断歩道では何もしないと減速しません。道路を渡る際はきちんと手を前に出して車を制止させましょう。
⑪ 留学を希望する後輩へアドバイス
本当におすすめなので必修科目を後回しにしてでも是非参加してほしいと思います。英語が不安と思う方に言いたいのですが、中国では基本英語が通じません。そのため、私は翻訳アプリを使って中国語で会話しました。翻訳アプリを使いこなせれば大丈夫です。
経済学には収穫逓減という言葉があります。同じ箇所に投資をしても利益の増分が小さくなるという意味です。ずっと東工大にいて得られる知見よりもこの清華大のプログラムに参加した人の知見ほうが間違いなく多いと思います。
参加する際の注意点は、英語科目が少ないことです。もし中国語に自信がなくて授業を受ける際はスライドを良く読んで翻訳アプリを使って受講してみてください。それでも完全には理解できないので先生に積極的に質問しましょう。一方的な講義授業よりも参加型の授業の方が理解が進むかもしれません。
GSS 2020 ―COVID-19パンデミック後の世界の新しい留学の形―

宮崎徹太郎
2020年7月20~28日の9日間、清華大学のオンラインサマースクール「Tsinghua Global Summer School 2020(以下、GSS 2020)」が開催されました。私は、今年3月のジョージア工科大学のリーダーシッププログラム、8~9月のKAISTのSummer Program(研究)に参加予定でしたが、両方ともCOVID-19により中止になりました。そんな折にGSS 2020を紹介して下さり、ぜひ参加したいと思いました。GSS 2020は清華大学の教授陣によるオンライン講義がメインでしたが、Lenovo未来センター(北京)とHuawai本社(深圳)のバーチャル見学、清華大学に関する様々な紹介など、内容は盛りだくさんでした。また、GSS 2020には79の国と地域の154大学から、1260人の学生が参加したのですが、世界のトップレベルの大学生達の多様性のある意見を聞くことができ、彼らの学びに対する積極性の高さを知ることができました。
GSS 2020では参加証明書、およびオプションで清華大学での1単位を得ることができましたが、そのためには、以下の2条件を満たす必要がありました。
① 以下の9つのテーマから5つを選び、それぞれでWorkshop、 Keynote、 Webinarの3講義を1つずつ受講。合計15+1(開会式)=16講義のオンタイム受講(または録画受講)
・Innovative Thinking Post-Pandemic
・Living Together Sustainably: Learning to Transform Oneself and Society
・The Economy Post-Pandemic
・Sustainable Development Post-Pandemic
・Artificial Intelligence Application and Governance
・Society Post-Pandemic
・Lifelong Learning and Development
・Future-oriented leadership
・New trend of globalization and global governance cooperation
② 約3000wordsのFinal Essayを提出。受講した5つの講義のテーマで約1500words、受講した講義以外の2つのテーマで約1000words、まとめ約500words。
(問題を提起し、その問題の性質と解決法、なぜ自分にとって重要かを記述)
講義はZoomまたはXuetangXで受講しました。ネットワークトラブルもありましたが、清華大学生のTAによる手厚いサポートによって混乱はありませんでした。使用言語は英語でした。WeChatでTAやグループメンバーと繋がることもできました。しかし、9日間土日含めてほぼ毎日、午後23時半まで講義に参加することは大変でしたので、私は録画視聴を適宜利用しました。その結果、東工大での研究活動と両立しつつ、すべてのGSS 2020の講義を見ることができました。さらに、今回GSS 2020に参加登録したことで、清華大学で公開されている「GSS 2020以外のオンライン講義」も受講可能になるという特典もあり、私は中国語を受講することができました。
このように様々な収穫があったのですが、清華大学は(GSS 2020を含めて)本気で世界に貢献しようとしているという姿勢が強く、日本のマスコミが行っている中国に関する偏向報道のようなネガティブな雰囲気はまったくありませんでした。むしろ、中国の世界での存在感は大きく、日本よりも積極的に国際的なリーダーシップを取っていることを痛感しました。それから「清華大学の講義では、3000-5000wordsのFinal Essayは普通」とのことで、清華大学生の勤勉さにも驚きました。今後も留学が困難な状況が続くかもしれませんが、インターネットによって日本にいながら世界中の人達と繋がることができるので、このメリットを最大限に活かすことがパンデミック後の世界では重要です。9日間という短い期間でしたが、「日本や東工大ももっと頑張らないといけない」と思わされるくらい刺激的で、国際的な視野を広げることができる充実したサマースクールでした。なお、Twitterで #TsinghuaGSS とキーワード検索すると一般公開されている情報を見ることができます。
Tsinghua Global Summer School 2020
http://goglobal.tsinghua.edu.cn/en/program/gss.tsinghua.edu.cn

S.K.
概略
東工大・KAIST(韓国)・清華大学(中国)の三大学合同で行われた冬季オンラインキャンプに参加した。内容は主に、特別講義、グループワーク、異文化理解セッションである。緊急事態宣言が発出されていたため、すべて自宅から参加した。
活動内容
- 特別講義
三大学の先生からの3つの講義。自分の専攻と異なる内容で、新鮮だった。 - グループワーク
三大学の学生6名+1名のメンターで取り組んだ。課題はSDGsのゴールを達成するクラウドファンディング案の提案である。優秀なチームメンバーと、非常に熱心なメンター(私のチームは東工大の先生)のおかげで、良いプレゼンテーションをすることができた。特に、一晩でウェブサイトのプロトタイプを作成したメンバーがいて、スキルの高さに驚かされた。 - 異文化理解セッション
東工大とKAISTが担当し、自国の文化を紹介した。東工大は、東工大のキャンパスツアーと折り紙体験をした。KAISTのセッションでは粘土でビビンバの小さな模型づくりをした。
プログラムを終えて
私が授業の関係で最後の懇親会に参加できなかったこともあり、今回はチームのメンバーと深い交流はできなかった。しかし、社会に出て海外の人とオンラインで仕事をする際は、このような関係性なのではないかと感じた。
オンラインで苦労した点
- "交流"の難しさを感じた。特に、KAISTの異文化理解セッションでは、手元の作業を進めながらZoomで会話をするのは難しく、メンバー全員が黙る時間もあった。私は会話のきっかけを作ろうと積極的に言葉を投げかけていたつもりだったが、あまりうまくいかずオンラインでの雑談の難しさを思い知った。
- 中国はウェブサービスの利用に制限があり、相変わらず不便そうだった。KAISTの学生がNotionというサービスを紹介してくれた。これは、同時編集ができるコラボレーションツールで、中国の制限に引っかからない。最終的には全員VPNに接続し、Googleスライドを利用した。
単位互換
大学院向けの単位がなかったため、申請していない。
同様のプログラムへの参加を検討している方々へ
外国人との英語でのディスカッションの機会は、あまり多くありません。オンラインキャンプはかなり密度の高い時間を過ごせるので、よい経験となると思います。ぜひ挑戦してみてください。

M.T.
① 参加プログラムの概略
- 東工大、KAIST(韓国)、清華大学(中国)の三大学からなるTKT CAMPUS Asiaは例年大学間で学生を派遣・受け入れしてきたが、コロナウイルスの世界的な感染拡大により、2020年はオンライン(zoom)で開催されることになった。
- Online Summer Camp 2020は3日間開催され、今年度留学予定だった学生、および過去にCAMPUS Asiaに参加した学生が参加した。
② 活動内容及び感想
l 1日目 自己紹介、特別公演1、プチ韓国語レッスン、工作(韓紙ランプ・組子)
l 2日目 特別公演2、韓国バーチャル旅行、チームプロジェクト準備
l 3日目 チームプロジェクト発表、表彰
今回初めてオンライン留学に挑戦しましたが、まるで皆が同じ場所にいるような感覚で、予想以上にインタラクティブな経験ができました。特に印象に残っているのは、Cultural Activity(工作)とチームプロジェクトです。Cultural Activityで使うキットは事前に自宅に配送されました。今回は韓国の伝統的な紙 韓紙を使ったハングルのランプと、日本の伝統技法 組子のコースターを作りました。各国の学生が「先生」となって、チームメンバーに作り方をレクチャーしながら組み立てていきました。メンバーのいる国が違っても、手元で同じ作品を仕上げていくという体験が新鮮で面白かったです。どちらも木を使った温かみのある作品で、今も部屋に飾っています。
チームプロジェクトでは「If people lose one of their five senses, how would the world change and how could technology help overcome the ensuing difficulties?」をテーマに、各大学の学生で構成されたチームでディスカッションとプレゼンテーションを行いました。1日目と2日目のプログラムが終わった後も、話し合いやスライドの編集を続け、皆が納得いくまでリハーサルを重ねました。限られた時間の中で、しかもオンラインで準備を進めるのは簡単ではありませんでしたが、皆でアイディアを出し合いながら、発表直前まで編集を続けました。無事に発表を終えた時には、安堵と達成感で皆自然と笑顔になっていました。チームの絆がさらに深まった瞬間だと感じました。結果発表では、画面越しでも皆が緊張している様子が伝わって来ました。ベストプレゼンテーション賞が発表されると、チームのWeChatで喜び合いました。住む国が違っても、母国語が違っても、直接会えなくても、英語というコミュニケーションツールを使うことで世界が一気に広がり、目標に向けて一緒に切磋琢磨できる仲間と出会うことができました。このプログラムに参加できて本当によかったです。コロナウイルスが収束したら、チームメイトの皆に直接会いたいと思います。
③ プログラム参加を終えて、自分自身の成長を実感したエピソード
マルチカルチャーの環境でも失敗を恐れず、チームをリードする自信がついたと感じました。私はプログラムに参加する前まで、リーダーシップを磨きたいと思いながらも、なかなか実践できていませんでした。しかし、大学生活で国際的な活動ができるのも今回が最後かもしれない、何か目標を立ててそれを達成したいと思い、チームプロジェクトのリーダーに立候補しました。どうしたら効率よくディスカッションを進められるだろうか、チームメイトは平等に意見を言えているだろうか、モチベーションを上げられているだろうか。リーダーの立場になると、今まで気にしていなかったことも自然と意識するようになりました。また、マルチカルチャーの環境でも、お互いを尊重しながらディスカッションできるように心がけました。チームメイトは非常に協力的で、フレンドリーで、私の至らない点も優しくサポートしてくれました。そのおかげで、私も失敗を恐れずに積極的にディスカッションに参加できました。ベストプレゼンテーション賞を獲得できたのは、素晴らしいチームメイトに恵まれたからです。皆で協力して目標を成し遂げることの楽しさを改めて感じました。
④ プログラム参加経験を今後どのように活かしたいか
多国籍メンバーでチームワークを築き、共通の目標を突破できた経験は、大きな達成感と自信に繋がりました。今回の経験は、海外のラボと共同研究について議論する際や、就職後のアサインメントで国際チームとコミュニケーションをとる際に活かしていきたいです。
⑤ オンラインで苦労した点(もしあれば)
・ディスカッション資料の共有(中国の学生にはVPNに繋いでもらわないとgoogle slideやgoogle documentで共同編集ができなかった)。
・回線が不安定で音声や映像が乱れる時があった。
⑥ 同様のプログラムへの参加を希望する後輩へアドバイス
参加を迷っているなら、ぜひ挑戦してほしいと思います。何事もやってみなければ分からないし、やらないで後悔するのはもったいないと思うからです。もちろん、今までの留学をオンラインで完全に再現することは難しいですが、オンラインにしかない利点もあります。コロナ禍でも今ある選択肢を最大限に活用してほしいと思います。
⑦ その他(あれば)
コロナ禍で今年は何もできないと諦めかけていた矢先に、このオンライン留学の案内をいただき、迷わず応募しました。3日間のプログラムが終わった今、参加できて本当によかったと改めて感じています。参加者の中には、CAMPUS Asiaを通じて知り合った友人もいて、画面越しに再会することができて嬉しかったです。
このような素晴らしい機会を与えてくださった各国のCAMPUS Asia事務局の皆様、先生方に感謝を申し上げます。ありがとうございました。今後もぜひ続けてほしいです!
TKT CAMPUS Asia Online Summer Camp 2020 ―日中韓の架け橋―

宮崎徹太郎
2020年8月17~19日の3日間、「TKT CAMPUS Asia Online Summer Camp 2020」がオンライン(Zoom)で開催されました。参加大学は清華大学(中国)、KAIST(韓国)、東工大(日本)でした。私は8~9月のKAISTのSummer Program(研究)に参加予定でしたがCOVID-19により中止になったため、その代替案として招待していただきました。東工大からの参加者は8名でしたが、事前にLINEで連絡を取り合いながら「文化活動(組子)」の準備を進めました。組子は「くぎを使わずに木材を組み立てる日本の伝統工芸」で、奈良の法隆寺の装飾に使われていたなど長い歴史があります。東工大生は、清華大学とKAISTの学生に組子の紹介と、組子コースター制作の指導を英語で行う仕事がありました。
1日目に自己紹介(英語、中国語、韓国語、日本語)、講義(AIを活用した交通政策の決定)、韓国語とK-POPの講義、文化活動(韓紙)、文化活動(組子)を行いました。AIの講義はQ&Aの時間もかなり長く、理解が深まりました。また、韓国語とK-POPの講義では、実際にK-POPを歌うなど実践的でした。韓紙・組子の制作は、日中韓混成のチーム毎に分かれて行いました。まず、韓紙の制作はKAISTの学生とスタッフの方に丁寧にご指導いただきました。そして、組子の制作は、シンプルな英語とカメラの映像を利用することが功を奏して、KAISTの学生の方・スタッフの方に無事に完成していただきました。この文化活動を通して親睦が深まったと思います。
2日目に講義(ウイルスが世界を変えようとしている。適者生存?)、Fun Activities(韓国の市場から実況中継)、Team Projectの話し合いを行いました。講義では、COVID-19の良い影響についてチームで話し合いました。原正彦教授(東工大)による「ニュートンはコレラで大学がロックダウンしている時期に、実家でりんごが落ちるのを見て万有引力の法則を発見した」逸話や、オラフ教授(公立千歳科学技術大学)による「社会的危機の時代には、それを解決するためのイノベーションが生まれる」というお話を聞き、科学者がリーダーシップを発揮しなければならない時代であると鼓舞していただきました。また、Team Projectで私はリーダーでしたが、英語のみで初めて会う外国人の方々を牽引するのはとても難しかったです。テーマ決め、タイトル決め、構成決め、役割分担決め、Zoomでのミーティングスケジュール決め、プレゼンテーション資料の最終版の制作など、半日でこなすのは本当に大変でした。私はチームメンバーに恵まれたので、助けてもらう場面も多々ありましたが、要所要所はリーダーが締めなければならないので、そのタイミングを読むことも重要でした。また、彼らとWeChat上で友達として繋がることができて良かったです。
3日目にTeam Projectのプレゼンテーションと評価・審査・表彰式、閉会式、記念撮影を行いました。私達のチームは「もしも触覚がなくなったら世界はどうなるか。その解決策は何か」というテーマでしたが、博士課程の学生が多いチームだったからか、論文発表のような真面目な発表になりました。一方、他のチームは動画や漫画などを制作していて、表現手法の多様性を感じました。私達のチームは運良く3位に入賞させていただき、象の形のBluetoothスピーカーをいただくことができました。なお、今回のプログラムはKAISTが主体的に動いて下さりました。例えば、TKT CAMPUS AsiaのTシャツや、様々なKAISTグッズを送っていただき、韓国人の温かさを感じました、このイベントは「日中韓の懸け橋」になると強く思います。韓国人や中国人は比較的に日本人と感覚が近いと思うので、たとえ英語が上手く話せなくてもコミュニケーションが取りやすかったです。オンラインで可能なことを最大限に利用した、充実した3日間だったと思います。

Yin Tuo
参加プログラムの概略
プロジェクトの期間は合計3日です。初日はまず自己紹介をしました。韓国と中国の学生が素朴な日本語で迎えてくれてとても親切と感じました。それから、清華大学の教授からのプレゼンテーション"AI-aided transportation policy decision: An example in the pandemic of COVID-19"を聞きました。最後に、グループで文化交流活動を行いました。私のグループにはKAISTの学生1人、中国清華大学の学生2人、当校2人がいて、Kumikoと韓国伝統的な木製のナイトライトを一緒に作りました。翌日、当校の教授の講演"A virus is changing the world. Survival of the Fittest. "を聞きました。短い昼休みの後、KAISTの学生が私たちを韓国の有名なスナックストリートに連れて行ってくれました。午後はグループディスカッションを行いました。今回のキャンプのトピックは、五感のうちの1つを失ったときに、科学と技術が人々が困難を克服するのにどのように役立つかということです。私のグループが選んだテーマは、世界中の誰もが聴力を失ったときに、科学と技術が人々のより良い生活をどのように助けることができるかということです。グループメンバーは活発に話し合い、夜遅くまで働きました。 3日目はグループプレゼンテーションの時間です。 5つのグループすべてが素晴らしいスピーチを行い、ほぼすべての学生がスピーチに参加しました。
プログラム参加を終えて、自分自身の成長を実感したエピソード
C O V I D−19のため、外の世界とのコミュニケーションが不足しており、ほとんどの時間を家に一人で勉強したり働いたりしています。 今回のキャンプ活動を通じて、グループメンバーとの深い友情を築くだけでなく、チームワークの精神も学びました。 キャンプのトピックが最初に発表されたとき、それは面白いトピックだと思いましたが、それも非常に広範で、エントリーポイントを見つけるのは難しいと感じました。グループメンバーと話し合った後、私は自分の専門分野から始めて、具体的な解決策を考え出しました。 同時に、清華大学の学生から論理的思考の能力を学び、KAISTの学生から創造性を感じました。
同様のプログラムへの参加を希望する後輩へアドバイス
スケジュールが許せば、サインアップしてみてください。初めて会う前に、韓国語と中国語の基本を学びましょう。たとえば、おはようございます。お世話になります。自己紹介の最後に韓国語と中国語の挨拶を追加したほうがいいです。グループディスカッションでは、全員がアイデアを提案するため、各グループは要約して記録するためのレコーダーが必要です。 そのため、Googleスライドなどの共有ソフトウェアを使用して、すべての重要なポイントを記録します。プレゼンテーションときは、複雑な言葉や文法よりも自分が話したいことを表現することが重要です。他の人が理解できるように、適度な速度で話します。

于 佳芸(YU JIAYI)
① 参加プログラムの概略
TKT CAMPUS Asia Online Summer Camp
② 活動内容及び感想
オンラインで東京工業大学、清華大学及び韓国科学技術院(KAIST)の学生と一緒に共に学んだり交流したりしました。
「コロナと科学技術」をめぐって専門家による講義とグループディスカッションがありました。情報量が多く色々勉強になりました。
「Culture activity」で日本と韓国の伝統的手工芸品である組子と韓紙ランプを作ってみました。完成品は今私の本棚に飾ってあって、それらを見るたびに楽しい思い出が浮かびます。
「Fun activity」でKAIST の学生が実際に仁川の新浦国際市場を案内してくれました。私たちはとても楽しみました。
最後に、各大学の学生と5 人グループを組んで、「もし人類が五感の一つを失ったら、世界はどう変わるのか。生じうる様々な挑戦に対して技術はどう役に立てるのか」というテーマに対して、発表及び質疑応答を行いました。非常に限られた短い時間で、価値観の違う人たちと理解し合う上、一緒にテーマ選びから満足できるプレゼンまでいくのは難しかったです。今回のグループプロジェクトは自分の知見を深め、視野を拡げ、物事を多角的に考える良い経験になったと思います。
③ プログラム参加を終えて、⾃分⾃⾝の成⻑を実感したエピソード
今回のプレゼン経験は私にとってとても新鮮でした。そして、今回のプログラムを通じて、自分の視野が限られていること、思考に偏りがあることを認めたうえで、自分の強みを再発見することができたのはとてもよかった思います。
まず、異文化に生じる多様性を感じました。最初は、日中韓三カ国の文化は近いし、私は在日中国人だし、国際交流はそんなに難しくないだろうと思いましたが、とても違いました。異なる学習環境にいる人の価値観・考え方の違う大きさに驚きました。問題の捉え方・策の創出法が違うから、意思決定のプロセスは思うようにいきませんでした。グループメンバー全員が合意できるプレゼンの内容と流れを決めるのは難しかったです。今まで積んだプレゼンの経験や常識など、自分がとても正しいと思うことでも、ほかの人にとって必ずしも正しくはないかもしれません。多様な人たちと触れ合うと、自分がどんな価値観を大切にしているのかを確かめ、自分の柔軟性も磨かれました。
また、メンバーのバックグラウンドの多様性から生じるアイデアの豊富さ、視点の幅広さはメリットですが、その一方、アイデアが多すぎて、その取捨と選択肢の洗い出しが難しかったです。さらに、メンバーそれぞれの価値観が違うから、アイデアの評価に関して合意に達するするのに時間がかかりました。
さらに、お互いの価値観の違いを尊重しつつも、色々気を使いすぎず、自分の考えをはっきり言うのは不可欠だとわかりました。今回の発表の準備時間は非常に限られていたので、討論のペースが速く、激しかったです。意見を言わずに黙っていては、誰も自分を正しく理解してくれないし、自分が望ましくない方向に流されるかもしれません。今回は激しい討論に身を置き、ある意味で差し迫った状況に置かれたことで、自分の考えをすぐ言えるようになりました。
最後に、自分の強みを再発見することができました。私は様々な活動やコンテストに参加してきて、ある程度身につけたスキルは今回のグループワークで発揮できたと思います。ごく普通で凡庸だと思っていた自身の知識やスキルも、実は広い視野で見れば類まれで有用かもしれない、自分が今のままでも何か貢献できる場所があるかもしれないと、自分に自信を持つことにもつながりました。
④ プログラム参加経験を今後どのように活かしたいか
将来国際交流する際に限らず、自分と違う意見や反対の声に直面する時に、感情的に反応するのではなく、相手の意見の背景にある論理や状況に思いを巡らせ、相手の思考を想像し、その人の考えを客観的に分析し評価するようにしていこうと思います。
また、異文化チームで意思決定をする上で、協力する意識は大切だとわかりました。国際交流する時お互いの違いに目を奪われがちですが、国や文化が違っていても、同世代の思いや感性には共通する部分が多くあります。みんなが共感できる点から始め、お互い理解し合って、少しずつ合意を達することができると思います。
⑤ オンラインで苦労した点(もしあれば)
中国にいる学生たちはGoogle とその関連サービスが使えないので、全員一緒に共同編集するのはできませんでした。情報をシェアする時は少し苦労しました。
また、オンラインはマルチタスクができやすい環境だから、このプログラム以外のことで忙しいグループメンバーがいらっしゃいまして、全員が力を揃えることが難しかったです。
⑥ 同様のプログラムへの参加を希望する後輩へアドバイス
勉強になるし、とても楽しいプログラムです!
私たちはいつか国際的なシンポジウムで活躍するような科学者になるから、違う背景の人と英語でディスカッションしたりプレゼンテーションを行ったりすることは重要だと思います。TKT CAMPUS Asia Online Camp はこれらのスキルを練習する場を提供しているので、難しいかもしれませんが、自己成長したい人はぜひチャンスを握って挑戦してみてください。

于佳彤(ウ カトウ)
① 参加プログラムの概略
TKT CAMPUS Asia Online Summer Camp 2020は、清華大学、KAIST(韓国科学技術院)、東京工業大学が協力して作った3日間集中キャンプである。CAMPUSアジアプログラムの入学希望者と卒業生が参加する、初のバーチャルサマーキャンプでした。特別講義、文化交流活動、チームプロジェクトで構成された。
② 活動内容及び感想
1) 特別講義
初日の講義のテーマは「COVID-19の例でAIを援用した輸送政策決定」でした。輸送システムのビッグデータモデリング、計画、管理、そして将来の流動サービスなどについて勉強した。二日目は講義を聞いて、コロナと科学技術をめぐってグループディスカッションを行った。グループで話し合い、色々な意見が出て良かった。
2) 文化交流活動
キャンプの初日の午後に文化交流活動があった。まず韓国のYonsei 大学の先生に4つ特別韓国文化レクチャーで、短時間で楽しくハングルを学び、一緒に韓国の歌を歌った。韓国語の歴史や由来、そして韓流文化を知って良かった。そしてKAISTの学生が主導になって、一緒に韓紙LED lampを作った。その後、東工大の学生が日本文化交流活動として組子の作り方を教えた。留学生である私はこのキャンプに参加する前に組子を知らなかったが、活動で他の学生に教えられるようになるために、組子に関する日本文化と伝統を色々調べて勉強した。組子の美しさと日本匠人の細かなところまで気を配る心に関心した。実際に韓国に行く機会がなかったが、最終日の午後にKAISTの学生のおかげで、ライブで韓国の市場を巡って市場の実況を見て雰囲気を感じた。
3) チームプロジェクト
「もし人類が五感の一つを失ったら、世界はどう変わるか。生じうる様々な挑戦に対して技術はどう役に立てるのか」をテーマに、グループ5人で発表した。違う大学と国から来た、様々な背景を持つ人々とコミュニケーションを取り、一緒にグループプロジェクトをやる貴重な経験だった。限られた時間内でトピックを決め、話し合い、調査研究し、発表することは、かなり挑戦的だった。自分の知識と想像力を使ってアイディアを出し合い、さらに様々な新技術を調べて、プレゼンを完成した。個人的および学問的な視野を広げ、将来のグローバル技術者として必要なスキルを磨く良い機会になったと思う。
このキャンプを通して、ネットワークを広げ、近隣諸国の文化を理解し、さまざまな知識を共有できる新しい友達に出会えた。非常に特別な3日だった。
③ プログラム参加を終えて、自分自身の成長を実感したエピソード
3大学の学生が一緒にやる特別なグループプロジェクトで、思い出になるエピソードが多かった。中に一番感慨が深かったのは、大学・学科、周りの環境、経験などが違う人の考え方と物事のやり方が違うことだった。
うちのグループ発表は優勝を獲れたが、その過程は順調ではなかった。発表トピックを決めた後、「科学技術はどう役に立てるか」など具体的な発表内容を決めるとき苦労したことが記憶に残る。たくさんの意見が出て、みんなそれぞれ違う見方を持っていて、良いプレゼンとグループワークの進め方に対するイメージも異なった。一度無意味なディベート気味の話になってしまい、プロジェクトがなかなか進めなかった。準備時間の大半を過ぎているが、発表内容が全然まとまらなくて焦っていた。しばらく休憩を取った後、共同の目標を明らかにし、また意見を交わした。みんな改めて自分の考えとその理由をできるだけわかりやすい説明で述べ、相手の見方を受け入れる姿勢でよくお互いの話を聞いた。意見の取捨選択が難しかったが、理解し合い、一緒にみんなが納得できるアイデアを考え出し、順調に発表内容を決めた。そしてメンバー各自の強みを活かし、それぞれ得意な部分を担当して効率高く発表資料を作り上げた。最終日に一緒に発表を完成し、満足のいく結果が得られた。
たくさんの意見と内容がある中、取捨選択が難しかったが、ある一部を切捨て、より良いものや相応しいものを選抜したからこそ、洗練された良い発表になったと思う。そして最終発表の前日に、調べたデータや思いついたアイデアなど発表に入れなかったものをスライドの最後にまとめて、質疑応答のために準備しておいた。発表が終わった後、疑応答が素晴らしかったと評価されて嬉しい限りだった。せっかく思いついて調べたから全部発表に入れたい、努力を無駄にしたくないという気持ちはあるが、裏の努力は決して無駄ではないと考える。
このキャンプを通じて色んな見方と考えに触れ、視野を広げて本当に良かったと思う。異なる国と大学から来た人の見方が違うし、国籍が同じでも教育環境と専門分野によって考えがそんなに違うことにびっくりした。何よりも、理解し合う姿勢の重要性が分かった。相手の意見をよく聞いて、自分の考えを誠実に伝える。先入観と思い込みを捨て、いろんな意見と考えを受け入れるよう、柔軟な頭で交流することが大切だ。その方が革新的なアイデアが生み出し、お互いに勉強できると分かった。
④ プログラム参加経験を今後どのように活かしたいか
今回のプログラムで学んだことを覚えて、次回このようなグループワークはさらにうまくいけると思う。また、改めて自分の考えを伝える力の乏しさを感じた。今後は如何にわかりやすい説明で自分の考えを相手に理解してもらうかを模索していきたい。言語の勉強はもちろん、表現力の練習もこれから頑張ります。そして、常に意識を高く持っている仲間との活動はとても刺激的だった。参加者みんな自分の専門に熱意を持っていることに関心した。これからも一生懸命勉強し、専門性を高めて行く。来年から研究室所属することになったら、熱意を持って研究に打ち込みたいと思う。もしまたこのような活動があったらぜひ参加したいと思う。
⑤ オンラインで苦労した点(もしあれば)
対面で紙に図を書いたり、体の動作で表現したりできなくて、考えを全部言葉で説明する必要があったので、苦労した。また、国の区域が違うため、オンラインで共同作業ができなかったことちょっと不便を感じた。
⑥ 同様のプログラムへの参加を希望する後輩へアドバイス
三日間という短い間ですが、楽しくて勉強になるプログラムになっています自分に自信を持って、積極的に違う背景を持つ人と交流したら、お互いに学び、成長できると思います。国際交流したい、何か新しいことを経験したい人、ぜひこのプログラムに参加してみてください。

S.K.
① 参加プログラムの概略
◇概要
チームプロジェクトを中心とした,3か国の学生交流・異文化理解のためのプログラム.
3日間オンラインで開催.
チームプロジェクトでは5人1チームで最終日の20分のプレゼンに向けて取り組む.
◇参加学生
清華大学(中国)・KAIST(韓国)・東工大(日本)の3大学の学生
CAMPUS Asia プログラムで今年渡航予定だった,または過去にCAMPUS Asiaに参加した学生
◇スケジュール
1日目 (10:00-17:00)
学生の自己紹介・Special Lecture・文化交流(ハングル講座/ランプ作り/組子作り)
2日目 (10:00-18:00)
Special Lecture・チームプロジェクトミーティング
3日目 (10:00-14:00)
チームプロジェクト発表会・結果発表/表彰
② 活動内容及び感想
かなり豪華な賞品が用意されていたことから,参加学生のモチベーションは高い水準で統一されており,やりやすかったです.もし,これが賞品も何もないイベントだったら,やる気のある人とそうでない人で分かれたのではないかと思います.
まとまった時間を使うプロジェクトがあったので,思っていたよりもチームメンバーのことを知ることができ,仲良くなることができました.
③ プログラム参加を終えて,自分自身の成長を実感したエピソード
チームプロジェクトではリーダーを務めました.このような多国籍のチームでリーダーを務めたのは初めてで,緊張しました.しかしやってみると,リーダーとしてやるべきことは日本人だけのチームのときと変わらないということを感じました.
④ プログラム参加経験を今後どのように活かしたいか
2020年9月から清華大学にオンラインで留学を予定しています.オンラインでも,意外と仲良くなることができるということが分かったので,留学中は積極的にコミュニティを探して参加したいと思っています.
⑤ オンラインで苦労した点(もしあれば)
参加場所は自宅だったので,良くも悪くも制限なく長い時間作業ができてしまうという点です.2日目の日中に思ったより作業が進まず,夜遅くまでスライドの修正やチームでプレゼンの練習をしたりしてしまいました.
清華大学の学生は中国にいるのでGoogleにアクセスできないという点です.オンラインで進めるならGoogleドキュメントやGoogleスライドは必須だと感じました.最後は,清華大学の学生はVPNに接続しアクセスしていたようですが,申し訳なく感じました.
対面のプログラムだと,食事や移動など雑談の時間が生じます.しかし,オンラインだとその時間がとりづらいので,文化交流(ランプ作りや組子作り)の時間があってよかったです.
⑥ 同様のプログラムへの参加を希望する後輩へアドバイス
オンラインのプログラムは,普通の留学に比べ圧倒的に参加しやすいというのがメリットだと感じました.
「現地に行くからこその留学の楽しさ・大変さ」のようなものは体験できませんが,語学力・グループワークの力試しや留学体験としては十分に楽しめると思います.
近くて重要な国、でも日本にいると情報があまりない国。実際に行ってすごさや実態を感じられる。

大久保 雄真
2019年9月~2020年1月まで清華大学の水利水電系に交換留学しました。土木の河川系と機械の水力タービン系を合わせた水利用に特化した学科に所属しました。学部生の卒業旅行で中国に行き、この国をもっと知ってみたいと思った事もあり清華大学に交換留学しました。中国語の学習歴は無く、留学前の中国語力は値段を聞いてその数字がわかる程度でした。
授業は留学生用の中国語の授業と英語で開講された黄河の文化と歴史という授業を受けました。それ以外の時間は研究室に行って調査を主に行っていました。研究室のゼミを通して日本では既存の構造物に対しての研究が多いのに対して中国では新規建設に対しての研究がメインであり国による研究対象の違いを感じました。実際に僕が中国にいる4ヶ月半の間で北京に空港が1港開港し、高速鉄道も1本開通しました。まさに今建設ラッシュであるというのを目の当たりにしました。また、清華大学は中国の中でも特に人工知能に力を入れている大学で、情報系の学科じゃなくても人工知能の研究をしています。ある学生から聞いた話では全ての学科で人工知能を利用・応用した研究がされているとのことでした。
課外活動として、東工大でも所属していたオリエンテーリング部に所属しました。2週に1回くらいの割合で土曜日に大会に出場しました。大会は北京市内の公園で開催されました。学外に出る機会がなかなか無い中、中国人学生とスポーツを通して交流することができ、とてもいい経験ができました。
東工大のOBとお会いできる機会があり、そこでお会いした方の紹介で中国に事務所を構える日本企業に訪問させていただき、海外駐在ではどのようなところで働いているのかというのを見させていただきました。また、清華大学にJリーグの村井チェアマンがお越しになって公演され、それに参加しました。他にも研究室の先生を日本から2名の先生が訪ねて三峡ダムを視察されるときに、同行させてもらいました。このように、日本にいてはなかなか経験できないことを経験することができました。
留学最後には友人が中国に遊びに来てくれて、一緒に観光しました。そのときには僕が注文したり交通を調べたりしました。このときに4ヶ月間での自分の中国語力の向上を感じることができました。まだまだ生活する上ではレベルの低い中国語ですが、それでも通じて実際に案内できた時はとても嬉しかったです。
留学後、中国がとても好きになり研究室の友達に『時間ができたらまた遊びにくるよ』と、言ったもののコロナの影響で全く会いに行けてないのがとても残念です。友達も「今度海外旅行するなら日本だから、日本を案内して」と言ってくれているため、また自由に往来できる日が待ち遠しいです。
このように、留学をすることで得られること、留学をしたからこそ感じられることは沢山あるので、もし機会があれば中国の留学もお勧めします。
留学に踏み出せない人に向けて

三山 幹木
2019年7月11日~24日で清華大学のサマースクール、「Tsinghua International Summer School」というテーマ研究型のプログラムに参加しました。このプログラムでは、7つの分野(Architecture, Creative City, Environment, International Relations, Industry Frontiers, Urbanization, Gender)から1つを選択し、そのテーマに関する講義、ディスカッション、フィールドトリップ、プレゼンテーションを通じて、現代中国の社会的な問題について学びます。
英語を使った交流や議論がメインとなるようプログラムが組まれているだけあって、先生や他の留学生との会話は必要不可欠です。自らの意見を英語で表現して、現地の学生や海外の学生と議論を交わすのはとても大変でした。それでも2週間で終わりが来ます。悔しい思いや恥ずかしい思いももちろんしましたが、最後までやり遂げたときには経験したことのない達成感と開放感がありました。
留学のハードルはそこまで高くありません。特にこのプログラムは期間・費用・内容的にも初めて中国に行く人や、初めて留学に行く人にはぴったりだと思います。
海外で勉強することに興味があっても、語学力の不安や、授業や研究・論文、就活への影響を考えるとなかなか留学しにくいなと考えている人ほど、一度留学生交流課に相談に行ってみるのが良いと思います。
留学で何が得たいか、何がしたいか、そういった自分の意志みたいなものが明確にあることの方が大切だと思います。東工大は支援も制度も厚く提供されているので、うまく利用して積極的にチャレンジしてみてほしいと思います。
包み隠さぬ激しさを持つかの国で、一人の日本人は何を思ったのか。

網崎 優樹
清華大学は今や言わずと知れた有名大学である。昨今の世界ランキングでは順位を上げ続け、国内では北京大学に肉迫するまでになった。なるほど確かに、世界の科学技術研究大学としてその名を聞かない日はない。
そんな清華大学へ東工大から留学した私であるが、いわゆる理系として勉強、研究をしに行ったのではない。私はあくまで理系を対象に研究を行なっているのであり、その意味ではおそらく文系と呼ばれるべきだろう。しかし、だからこそ清華大学がトップレベルでいられるゆえんを垣間見ることができたのではないかと思う。分野を問わず、探して見つからないものはないと言えるほど多様な文献を参照することができ、大いに前進することができた。文系は北京大学、理系は清華大学と聞いたことがあったが、その実、清華大学は裾野をかなり広く持つ大学であった。
縁あって中国の近現代科学史を授業で学びもしたが、5ヶ月という滞在期間は、一つの国のことを知るには短すぎると言って良い。私がこの間に見たものは、中国人が日々肌で感じる"までもない"ことだろう。しかしその逆のこと、私自身が何をどのように見ているのかということへの発見は、5ヶ月を通じて熟成を続けている。
自分の生活圏を出た先にあるものを実際に見ること自体が、留学の大事な意義である。しかし、それを通じて私自身を形作るものを知るという内側への展開も、また別角度からの国際化と言えるのではないかと思う。
留学に行こうか迷ってるなら絶対に行くべし。絶対に楽しいから。
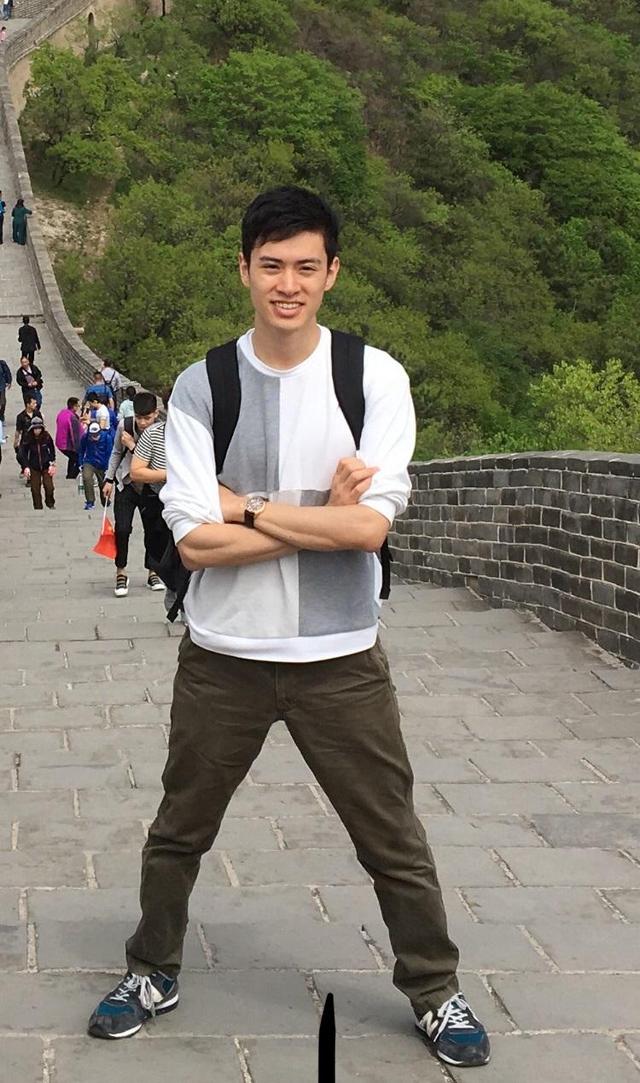
藤井 雄輔
化学工学科4年の藤井雄輔と申します。2018年2月~6月に中国の清華大学に留学していました。中国語学習歴はありませんでした。中国到着時より中国語の学習が始まりました。最大、中国語しか通じない場所に行った時は「これ」とジェスチャーで乗り切っていました。他の留学生はもちろんですが、清華大学の学生は英語がとても上手だったので、コミュニケーションは英語でした。
大学では化学工学の研究室に所属していました。研究テーマは「ナノ金属粉末で処理されたM13ファージの挙動」という生物に関するものでした。実は化学工学のなかに生物の分野を取り扱うものがあり、私は学部3年までそれを学んでいなかったので、文字通り知識ゼロから研究をはじめました。最初は論文、教科書、実験手引き書を読み、一つ一つの実験に時間がかかりましたが、研究室のメンバーのサポートもあり最終的には先生とテーマについて簡単なディスカッションができるようになりました。
空き時間には、友人と旅行、ひとり旅、北京に進出している日系企業の訪問をしていました。出会う人々、一緒に旅行に行った人、聞いた話、見たもの、すべてが新鮮でした。
4か月の短い間であったが、毎日が充実していた。一緒に過ごした留学生とはとても仲がよくなり、将来お互いの国で会おうと約束し、今でも連絡を取り続けています。もうすでに6人ほど日本を訪ねてきてくれました。今度は私が彼らの国を訪ねる番です。
自分の目で見ることで初めて「等身大」の中国を知ることができた。留学によって多くの思いもよらない経験に巡り合うことができ、予想以上に密度が濃く、実に充実し成長できた留学ができたと思う。

田中 道大
双子座流星群がとてもきれいに観察できるほど、北京の空気はきれいであった。と書けば多くの読者が驚くのではないだろうか。
僕は学部3年後期の間、清華大学の化学工程系に留学した。初めての中国渡航、さらに第二外国語で中国語を選択していなかったために、語学は初級の中国語から学び始めた。毎週午前中は専門の授業と中国語の授業を履修していたが、中国語に関しては、中国人の友達と中国語で意思疎通ができないことへの悔しさと、なんとか理解してもらえたときのうれしさ、達成感がばねになり、勉強を続けることができた。振り返って見ると、留学中に5回ものプレゼンを中国語で行っていたことには自分でも驚いた。
研究面では学部生であるにもかかわらず、大学院生と同じ環境での研究をさせてもらえた。研究テーマは「ナノコンポジットハイドロゲル」という高分子化学の一分野で、近年盛んに研究されている分野の一つでもある。初めての研究室配属ということになり、最初は英語の論文読み、実験計画などひたすら困難の連続であった。しかし次第にそれらを自分自身でこなせるようになり、最終的に実験報告書を英文でまとめて提出したことは自信にもなった。
北京への留学生だからこそ得られる経験も豊富であった。特に日中関係に関係する交流会や活動を通して多くの社会人、学生と出会い、話を聞くことができた。留学前は専門も違うしなかなか足を踏み入れがたいと感じていた日中関係に対しても見識を広め、関心を持つようになった。やはり直接中国に行き、自分の目で見ることで初めて「等身大」の中国を知ることができたのだと思う。
余暇の時間は適度に取るようにし、運動や昔の北京の街並みを残した住宅街、有名どころの観光、北京の特産品の食べ歩きや友人との交流を楽しんだ。遊園地のアトラクションでは、乗り物が滝から落ちるたびに大きな水しぶきを上げ、見もの客に大量の水しぶきを浴びさせたり、ディズニーとは全く関係のない池のほとりにあるベンチはミッキーとミニーの像に支えられている、といった中国らしさは見ていて面白い。
ここに書ききれないことはまだまだたくさんあるが、まとめると、留学によって多くの思いもよらない経験に巡り合うことができ、予想以上に密度が濃く、実に充実し成長できた留学ができたと思う。
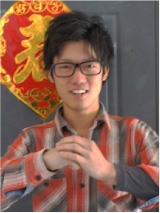
中村 富郎(中国・清華大学)
苦しいこともありましたが、留学したことで、視野が広がり、自らの強み弱みをこれまで以上に認識できるようになりました。私は学部生だったので、研究室には所属せず、授業のみ受講しました。中国語学習経験があったため日常会話は問題ありませんでしたが、授業では大変苦労しました。また、清華大学日本人会に短期留学生代表として関わったことは、非常に大きな経験になりました。予想もしない経験を積めるのが留学です。少しでも興味があれば是非挑戦してください。
・授業で「日本の大学とは違うな」と思ったことはありましたか?
・勉学以外で、留学してよかったと思えたエピソードがあれば教えてください。
| 7:30AM~7:55AM |
起床・身支度・軽い朝食 |
| 8:00AM~10:15AM | 授業(1限):専門授業 ※1回につき135分と90分の授業とがある。 |
| 10:20AM~11:50AM | 授業(2限):語学(留学生ばかりの授業) |
| 11:50AM~1:05PM | 昼食(友人たちと食堂で大皿を囲んで) 寮に戻って教科書の入れ替え、課題の取り組みなど |
| 1:05PM~2:35PM | 授業(3限) |
| 3:00PM~6:00PM | フリータイム (学内でサッカーやバスケに興じる。 後期は学内外の学生らとともに文化祭を企画、その準備など) |
| 6:00PM~7:00PM | ランニング(課題として毎日1km程度、グラウンドを周回する) |
| 7:00PM~8:00PM | 夕食(寮の留学生たちで大鍋でカレーを煮込み、 カレーパーティーを開いたりすることも) |
| 8:00PM~11:00PM | フリータイム (寮で課題の対応など。週末は近所のバーに友人と出かける) |
| 11:00PM~0:00AM | 入浴・明日の準備・就寝 |
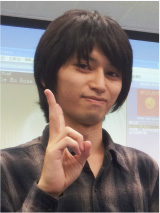
梅津 純平(中国・清華大学)
留学生寮に滞在しているので、周りには様々な国籍の学生がいます。中国語だけでなく英語も学ぶために、寮の友人とお互いの言語を教え合っています。また、現地学生のサッカーサークルに所属しています。こうした留学先での経験は研究室での研究活動や専門授業の受講とはひと味違ったものです。清華大学は非常に国際色豊です。研究室にこもるだけでなく、外に出て積極的に異文化交流することをお勧めします。
・授業で「日本の大学とは違うな」と思ったことはありましたか?
・勉学以外で、留学してよかったと思えたエピソードがあれば教えてください。
| 7:30AM~7:55AM | 起床・身支度・軽い朝食 (寮は学内にあるので5分もあれば教室に移動可能) |
| 8:00AM~9:30AM | 授業(1限):中国語授業 |
| 9:45AM~11:50AM | 研究活動 |
| 11:50AM~1:30PM | 昼食(研究室の友人と)、所属するサッカーチームの試合、練習 |
| 2:00PM~6:00PM | 研究活動 |
| 6:00PM~7:00PM | 夕食(留学生の友達や語学パートナーと) |
| 7:00PM~9:00PM | 研究活動 |
| 9:00PM~9:30PM | 寮の隣のテニスコートで壁打ち |
| 9:30PM~11:00PM | フリータイム、主に中国語や英語の勉強 |
| 11:00PM~0:00AM | 入浴・明日の準備・就寝 |