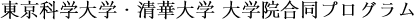学生たちの声
![]()
新たな研究環境に、胸はずむ!
本プログラムに参加する学生たちは一様に行動力があり、チャレンジ精神に溢れています。本プログラムを志望する動機は「中国(日本)での研究環境に興味がある。」「中国(日本)の文化を体験したい。」「あえて厳しい環境に身を置くことで自己研鑽をしたい。」など様々です。
日本からの学生の派遣は、2005年8月からスタートし、毎年約10名の学生が北京の清華大学に滞在し、研究活動を行っています。一方、中国からの学生の受入は、2006年3月からスタートし、こちらも毎年約10名の学生が来日し、東京科学大学で研究活動を行っています。
修了生からのメッセージ ※内容は取材当時のものです。
ナノテクノロジーコース - Nanotechnology –
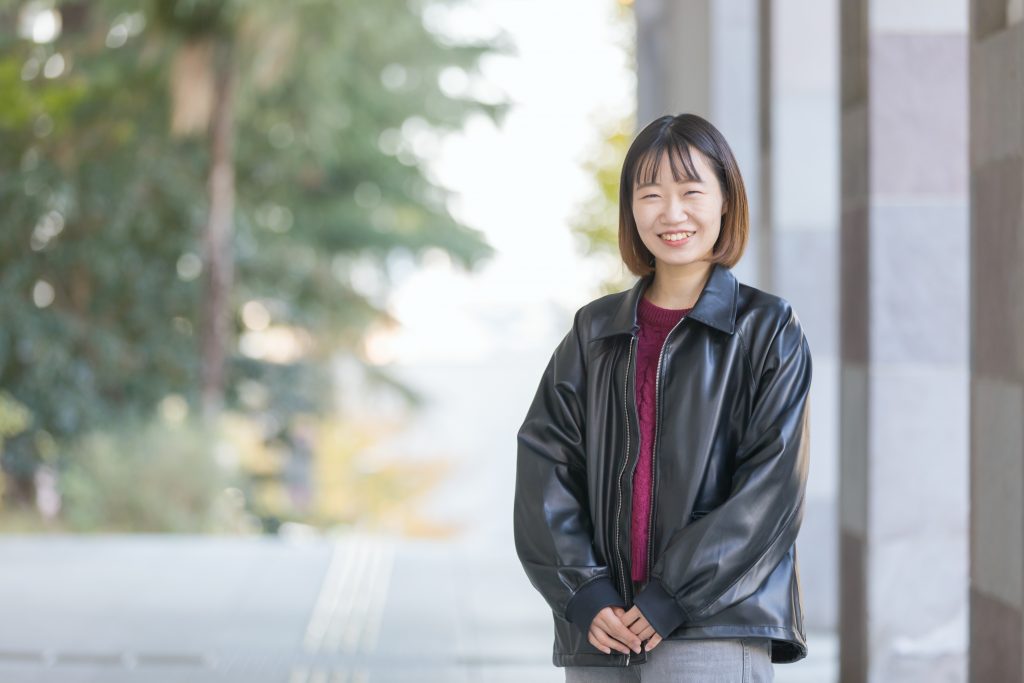
東京科学大学(東京工業大学)18期生
野中 菜々子(NONAKA Nanako)
世界最高峰の研究環境で加速させた持続可能な社会への探究
私はエネルギー化学を専攻しており、特に蓄電池の研究をしています。近年、新聞やニュースを通して中国の車載電池シェアが急速に拡大していることを知り、その技術発展の鍵である研究力を自分の目で確かめるために、中国トップレベルの清華大学への留学を決意しました。清華大学での研究生活は、日本の大学院で培った専門知識を活かしつつ、世界最高峰の研究環境に身を置く貴重な経験となりました。苦労した点としては、清華大学の学生の学習意欲の高さに圧倒され、自分の研究への取り組み方が甘かったと痛感したことです。しかし、この経験が「もっと頑張らなくては」という強いモチベーションにつながりました。留学前、私が抱いていた「世界中の人々が平等に豊かな暮らしができる社会を実現したい」というキャリアビジョンは、清華大学での経験を経て、より確固たるものとなりました。中国各地への旅行を通じて異文化に触れたことも大きな財産です。このプログラムは、自己のキャリアを世界レベルで再定義したいと考えている学生にとって、最高の舞台です。

清華大15期生
陸昳叡
LU Yirui
東工大の研究室はとてもいい実験環境で、先生や学友と実験中の問題を検討することができるので、とても実りがありました。日本人は細部に真摯に取り組んでいると思います。休日に、色々な美術館に行きました。日本の芸術家の自然と建築と芸術を完璧に結びつけることがとても好きです。そして、Estee Launder日本研究開発センターで短期インターンとして日本人と一緒に働きました。学生から社会人まで、勉強するべきことがたくさんあり、いい経験になりました。 この一年間で、成長する事ができ、視野も広くなりました。心から感謝しています!
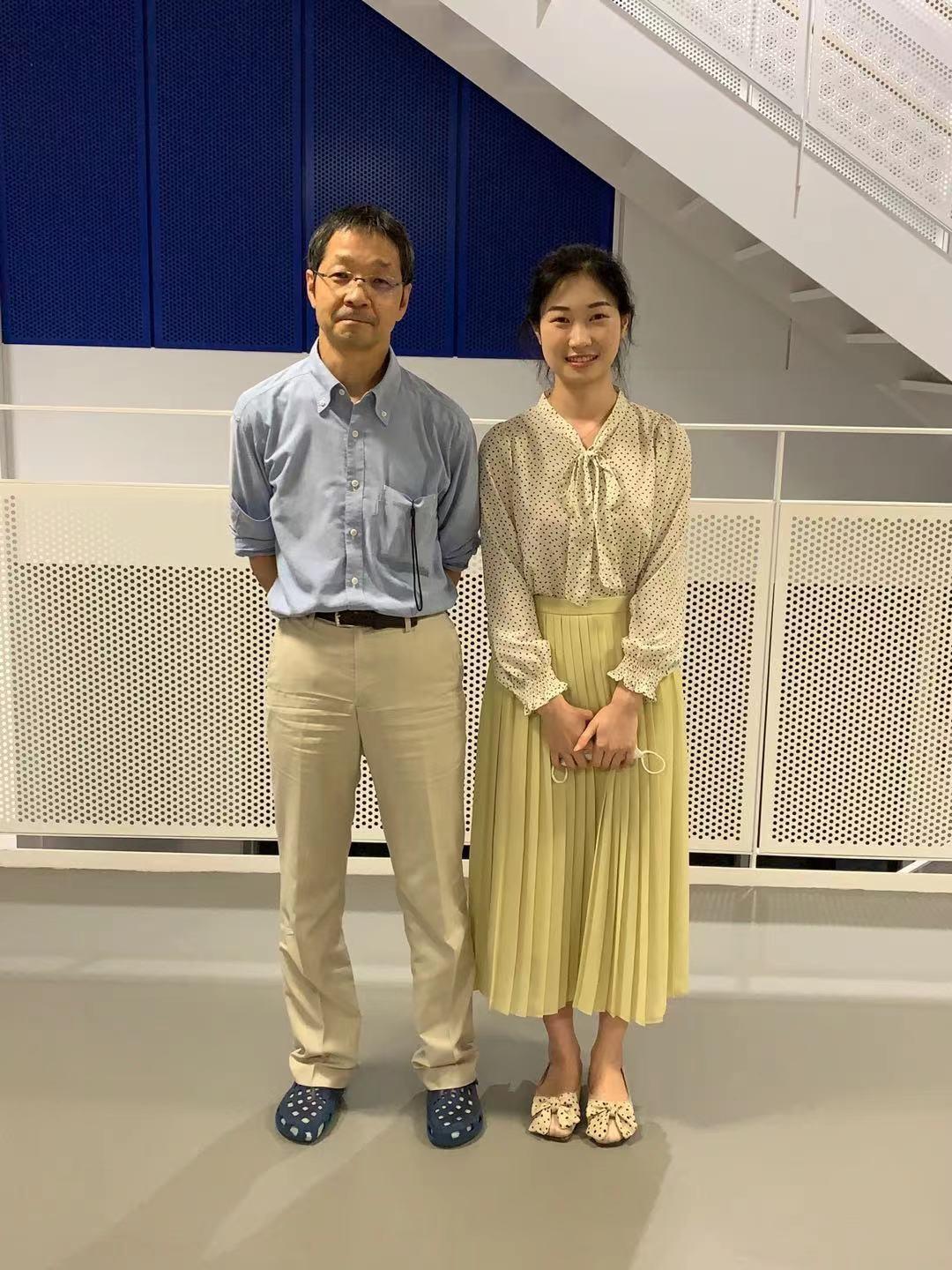
清華大15期生
黄 宇
HUANG Yu
私は材料コースのホアンユイともうします、2019-2020年にすずかけ台キャンパスの舟窪研究室で勉強しました。去年の日本での生活は、本当に楽しかったです。研究室の先生や学生達は、熱心で、優しいです。東工大での研究活動で、先生や先輩の助けがあり、研究テーマが順調に進み、とても実りのある生活でした。研究以外にも、休みの日は研究室の仲間と日本の文化や習慣を体験して旅行に行きました。コロナの影響であまり旅行ができなかったのは残念でした。 私は日本で有意義な研究および日常生活を行えました。再び、日本で研究を行ったり、遊びに行きたいです!

東工大15期生
臼井 慧
USUI Kei
①プログラムに参加した理由
本プログラムの説明会に参加したときに留学から帰国した先輩の話を聞き、研究や日常生活において日本ではできない色々な経験を積めると感じ、参加しました。
②後輩、参加を考えている人たちへのアドバイス
留学中の生活は言葉が通じないことや文化の違いなど戸惑うことが多くありました。さらに、短い期間で研究結果を出さなくてはいけないなどプレッシャーもありましたが現地の先生や学生の力を借りて乗り越えることができました。研究室の仲間や一緒に講義を受けた友達とは学外へご飯や観光など遊びに行く機会もたくさんありました。苦楽を共にした仲間を得ることができるのも大きな魅力だと思います。このプログラムは先生方や事務員の方のサポート体制が充実しており、現地の先生とのマッチングや奨学金制度の利用においてなど大変お世話になりました。この留学に興味を持った方やこれから留学する方には早めに行動することをお勧めします。私の場合はコロナウイルスの影響で渡航が途中で打ち切りになりましたが渡航前に研究テーマを決めたり、現地で早めに卒業単位をとっておいたため学位も取得できました。

東工大15期生
平林 透
HIRABAYASHI Toru
①プログラムに参加した理由
国内外で活躍できるような人になりたいと考えたときに、欧米でなくアジア中国で最高峰の大学で挑戦することは特別で他にはない経験を積めると感じ参加しました。多くの中国の友人が後押ししてくれたことも理由の一つです。
②後輩、参加を考えている人たちへのアドバイス
本プログラムは通常の修士課程生の友人らと比べて卒業が遅れてしまうことや、清華大学の学位取得条件が日本の大学と比べてかなり厳しいため修了が保証されてないなど、参加するのをためらってしまう理由が多々あると思います。しかしプログラムに一緒に参加し苦楽を共にする同期は一生の友人となるでしょうし、海外での厳密な修了条件をクリアする経験は将来の博士・社会人時代の両方に資すると感じています。また先生方や事務員の方のサポート体制・奨学金が充実しており、留学に際して研究や興味のあることに集中できる環境が整っていることも魅力の一つです。ただ百聞は一見に如かずなので、まずは身近な中国人を見つけて少し話してみることから始めるといいと思います。そんなちっちゃな経験が一生の経験の入り口になるかも!
バイオコース - Bioscience and Biotechnology –

東京科学大学(東京工業大学)19期生
岩田 竜馬(IWATA Ryoma)
潤沢な資金と速度を誇る環境で、中国研究の最前線に立つ
大学院進学にあたり「海外で研究したい」という思いが強く、幼少期を過ごした経験から、中国を「原点に立ち返る場所」として選びました。清華大学の魅力は、潤沢な研究資金と学生の活気です。私の所属研究室は応用研究が中心で、産学連携が非常に盛んなため、成果が出るとすぐに工場でのパイロット試験が行われ、実用化に直結するスピード感がありました。国から重点研究への支援があり、シーケンス解析といった実験でも「コストよりも速度」が最優先されていたのが印象的です。日本の研究の「精密さ」と、中国の「スピード感」の良い部分を同時に吸収できる、貴重な経験でした。また、広大なキャンパス内には寮、食堂、床屋、スポーツ施設などが揃っており、学業と生活が密接につながっています。そのため、学生同士が自然と交流する機会が増え、共に学び、共に生活する仲間意識が育まれる環境でした。 写真: 東京科学大学 学位記授与式 2025.9.22

東京科学大学(東京工業大学)18期生
長谷川 佳保(HASEGAWA Kaho)
困難を乗り越え培った「不屈の精神」と多様なキャリア観
元々海外に行きたい気持ちがあり、中国語を第二外国語で学んでいたことと、清華プログラムであれば正規生として海外の大学院に通えることが魅力的だと感じ、このプログラムを選びました。清華大学は、理系も文系も芸術系の学部も揃っており、多様な考えを持つ学生と出会えるのが最大の魅力です。また、広大なキャンパスには、10か所以上の図書館があり、深夜12時まで開いている施設もあるため、いつでも勉強できる環境が用意されています。留学中、「突然物事が決まる」という中国特有のダイナミズムの中で、研究室の工事により実験ができなくなるという予期せぬ困難にも直面しましたが、そのような環境に身を置いた経験が、「今ある環境の中でなんとか戦う術を考える」という前向きな姿勢と、「不屈の精神」を培ってくれました。この経験を通じて「海外とつながる仕事がしたい」と考えるようになり、外資系企業を選択。中国で友人にメイクをして元気づけることが出来た経験から、化粧品会社への入社を決意しました。プログラムで得たタフネスと、多様な学生との交流で培った国際的な視野は、現在のR&I職の基盤となっています。
写真: かけがえのない友人たち(長谷川さん左端)

清華大15期生
王 彦珺
WANG Yanjun
清華大学の学部3年生の時、東京工業大学と清華大学の大学院合同プログラムについて知り、参加を希望しました。 邢新会先生の推薦で、私はプロジェクトにスムーズに参加しました。修士課程1年生の時、清華大学で日本から留学してきていた菱川さんと知り合いました。 私たちは良い友人となり、清華大学化学学部の新入生活動やコース研究のおかげで、言語と学力が成長しました。 東京工業大学に留学した1年間は、充実した安心感を感じました。 学業では初めて全て日本語の授業に参加し、日本語能力が飛躍的に向上しました。 私が所属した山本研究室は、アカデミックな雰囲気だけでなく、リラックスした課外活動もたくさんあります。 研究室での食事(ハッピー・フライデー)は月に1回、定例会や忘年会があります。 新型コロナウイルスの流行の影響により、学校は一時的な閉鎖と長期の登校者数管理を行いました。東工大が講じた多くの予防策は、同期のプログラム生の健康と安全を確保し、日本でのプログラム期間を無事に終了し、中国へ帰国することを可能にしました。 プロジェクトの先生たちに、誠に感謝いたします!
社会理工学コース - Decision Science and Technology –

東京科学大学(東京工業大学)15期生
西島 光洋(NISHIJIMA Mitsuhiro)
ダブル研究で探求した、未来の専攻分野への決断
大学院でどの分野を専攻すべきかを決めかねていた私にとって、東京科学大学と清華大学で異なる研究に取り組める本プログラムは、自己の適性を見極める最高の機会でした。東京科学大学では数理最適化に関する研究を、清華大学では計算言語学に関する研究をそれぞれ実施しました。このダブル研究の経験を通して、「より数学寄りの研究がしたい」という自身の興味と適性に確信を得て、博士後期課程の専攻分野を決断できました。清華大学は非常に多くの種類のジャーナルを購読しており、論文閲覧で困ることがなかったのも、世界トップレベルの研究環境を象徴する大きな魅力です。本プログラムでは、単なるダブルディグリーの取得に留まらず、二つの研究テーマに挑戦し、国際的な環境で自らを客観視することで、キャリアの羅針盤を得ることができました。将来の進路に迷いがある学生こそ、ぜひ挑戦してほしいプログラムです。
写真: 留学中に哈爾濱へ旅行

東京科学大学(東京工業大学)15期生
杉岡 隆(SUGIOKA Takashi)
超一流の知の探求が拓いた、グローバルキャリアへの道
中国の思想と歴史への強い興味から、人文・社会科学の分野においても超一流の教員が在籍する清華大学での学習機会に魅力を感じ、本プログラムに参加しました。留学生活で最も刺激的だったのは、清華大学での研究です。指導教員との議論は非常に深く、「真理を探究」する姿勢に感銘を受けました。また、中国内外から優秀な学生が集まる教室で、価値観や専門知識が異なる学生たちと学ぶ経験は、国際社会で働くための土台を築いてくれました。苦労した中国語も毎日欠かさず学習し、大きく向上することができました。清華大学のキャンパスは、「水木清華」に由来する美しい庭園をもとに発展しており、学生が勉学やスポーツに励むための、宿舎、学食、運動施設などが全て揃った「一つの美しい街」のようでした。この最高の環境で得た知見は、修了後のキャリアに直結しました。就職活動では、「アジア随一の大学で最も優秀な学生たちと切磋琢磨して修士課程を修了したこと」「勢いのある大国・中国への深い理解」が大きなアピールポイントとなり、現在のグローバルなコンサルティング業務に活かされています。
写真: 西安の陝西省歴史博物館前にて
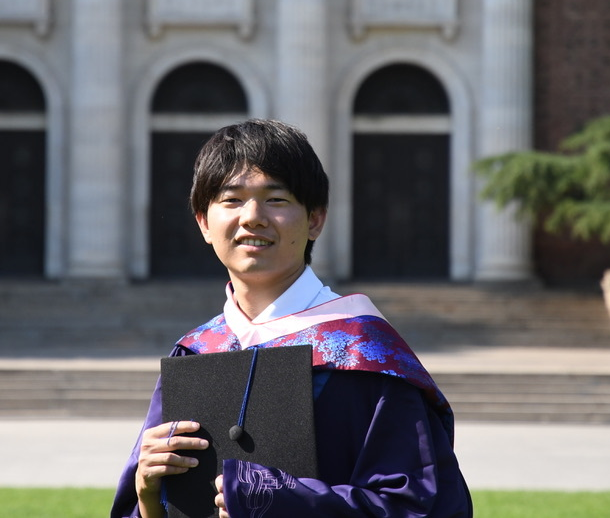
東工大17期生
三浦 皓
MIURA Ko
国内外で活躍でき、アジアを代表できる人材になりたいと考える中で日中のトップ校それぞれで修士号を得ることができる本プログラムに出会い、受験を決めました。 コロナ禍の入学で渡航の目処が立たない状態が1年以上続きオンラインでの学習が続きました。東工大の授業と清華大の授業を同時並行で進める時期や、東工大の修士論文と清華大学の中間発表を同時期に行うなどタフネスが要求される時期もありました。ビザの発給が再開され、やっとの思いで清華大学の最後の学期を過ごせました。 2年半の期間で2つの修士号を目指すのは簡単なことではありません。しかし、このプログラムを通して得られる経験は研究のみにとどまりません。指導教員や事務室の皆様の献身的なサポートで修了に至ることができました。この経験を活かして、清華OBとしても東工大OBとしても社会で活躍していきたいです。
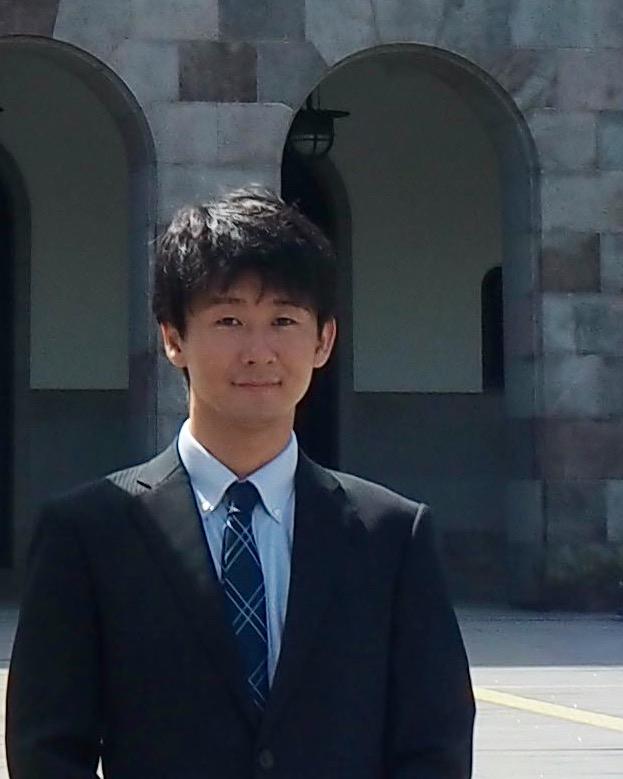
東工大16期生
渡辺 広樹
WATANABE Hiroki
コロナの影響により、当初考えていた様な中国への留学は叶いませんでしたが、東工大清華プログラム事務室の皆様のサポートと、清華大学のご厚意により、卒業間際にごく短期間ではありましたが、清華大学を訪問することができました。 中国について学び、中国の人々と交流した経験は、自分にとって大きな財産になりました。今後も本プログラムを通じて得たスキルや人との繋がりを博士課程での活動に役立てていきたいと思います。 決して楽ではありませんが、人として成長する絶好の機会を提供してくれる素晴らしいプログラムです。言葉や自信は後からついてきますので、是非一歩踏み出してみてください。

清華大15期生
李丹
LI Dan
鄭美紅先生のおかげで、私は清華大学-東京工業大学の大学院合同プログラムに参加して、東京工業大学と縁を結ぶことができました。このような貴重な経験をさせていただき、本当にありがとうございました。日本に行く前、留学生活への期待とともに不安も感じていました。幸いにして、日本の指導教員の林直亨先生や研究室の学生たちはとても親切でした。彼らの助けで、私はすぐに日本での生活に慣れました。東工大で清華と違った授業を受けてとても楽しかったです。授業を通じて日本の文化を知り、日本語も勉強しました。中国と違って、日本では旧歴の正月は祝わないので、あの日まだ授業がありました。私が感動したのは、日本語の先生は授業が終わる時、わざわざ中国語で新春のお祝いをしてくれました。 研究の上で、林直亨先生は私の考えをとても支持してくれて、大変お世話になりました。林先生は真面目で博識なうえにユーモアもあります。先生の指導の下で働くことができて、とても光栄に思います。私の研究計画はコロナウイルスのために影響を受けましたが、林直亨先生はいつも丁寧に指導してくれました。 東工大・清華大学大学院合同プログラムを通じて、大川玲さんや丸茂勇斗さんなどと出会えて、貴重な友情を得ることもできました。彼らは留学生として清華にいる時から、我々は知り合いになりました。わたしは日本にいるとき、彼らもたくさん助けてくれました。日本を離れる前にも、日本人の友人と一緒に日本で短い観光をしました。また、プログラムの王亜民先生の紹介のおかげで、「アジアの新しい風」に参加しました。組織のペンフレンドが日本語の練習を手伝って、日本の文化を紹介してくれました。寿司作り、みかん狩りや博物館見学などさまざまな活動が私の日本生活を豊かにしてくれました。 このプロジェクトは私の個人的な成長を助けてくれましたし、素晴らしい思い出もたくさんできました。このプロジェクトに参加できてとても光栄と思います。

清華大15期生
葛諾
GE Nuo
東工大で過ごした充実した楽しい時間を忘れる事はありません。常に私を励まし指導してくださった先生方や、いつも助けてくれてそばにいてくれた友人たちに心から感謝します。 COVID-19の流行が早期に改善し、日本とそして美しいキャンパスに戻り先生方や友人たちと再会できることを楽しみにしています。

東工大15期生
中村 璃沙
NAKAMURA Risa
①プログラムに参加した理由
研究テーマとして人の国境を超えた移動に興味があり、有数の移民排出国である中国での研究が有益になると考えました。世界ランキングでも上位に食い込むアジア有数の教育機関である清華大学への学位留学は、学術的な面に加えて、英語以外の語学を習得する良い機会であると捉えていました。また、学部での米国留学では、自分が日本人よりもアジア人であることを感じる部分が多く、アジア諸国の中に飛び込んでみたらどうなるのかという好奇心がありました。
②後輩、参加を考えている人たちへのアドバイス
両方の大学院で単位を取得しながら修士論文を書き終えることは想像以上に大変で、且つコロナで実際の北京滞在が半年程度になり、モチベーションの維持に苦戦しました。どのような環境下でも「なんとかなる、なんとかする」姿勢を身に付けられたこと、実際に無事2つの修士号を取得できたことは、今後の自分にとって大きな自信になると思います。能動的に動き続くことが求められますが、事務室の方や先輩方のサポートが充実していますし、何より自分の行動次第で経験の質も量も広がるプログラムです。
関連リンク ※内容は取材当時のものです。
■世界で活躍する同窓生 東工大・清華大学大学院合同プログラム修了生
- 東工大 1期生 (ナノテクコース)河野 俊司さん
- 清華大 2期生 (社会理工学コース) 高 揚さん
■国際交流TOPICS_ 東工大・清華大学大学院合同プログラム
◇参加学生からのメッセージ
- 東工大 8期生 (ナノテクノロジーコース) 尾田 良晶さん
- 東工大 8期生 (バイオコース) 森川 裕一さん
- 清華大 9期生 (社会理工学コース) 周 皓昕さん
■国際交流 特色ある国際交流の取り組み_ 清華大学との大学院合同プログラム
◇修了生からのメッセージ
- 東工大 12期生 (ナノテクノロジーコース) 鈴木 崇大さん
- 東工大 9期生 (バイオコース) 梅津 純平さん
- 東工大 13期生 (社会理工学コース) 有満 勇人さん
- 東工大 8期生 (社会理工学コース) 林田 駿弥さん
- 東工大 8期生 (バイオコース) 藤 亮介さん - (写真)東工大9期生 南 隆之さん、梅津 純平さん